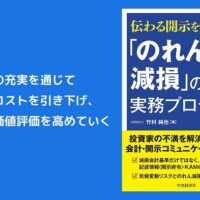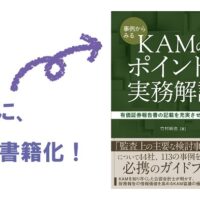英語の構造と似ているもの。それは、法律。そんなことを感じたことはありませんか。今日、ふと手にとっていた英語の解説書から、英語と法律とが似ていることに気づきました。
ボクが手にした本は、『越前敏弥の日本人なら必ず誤訳する英文 決定版』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)。著者は、文芸翻訳者の越前敏弥サン。『ダ・ヴィンチ・コード』の翻訳も手掛けていらっしゃいます。石川県は金沢市の生まれと聞いて、親しみを勝手に覚えています。


その本は、誤訳しそうな英文について、正しい翻訳の仕方を教えるもの。この中で、否定に関する解説に目が止まりました。ざっくり言えば、何かの文章の後に、NotだとかNeverなどの否定の言葉があっさりと用いられているときには、元の文章の構造を省略している、というもの。
簡単な構文でいうと、”A is B. Not C.”というときの2つ目の英文は、”A is not C.”を省略したものだと説きます。これくらいシンプルなら、構文が省略されていると意識しなくても意味を理解することができます。
しかし、少し込み入った英文だと、2つ目の英文が省略しない場合にどのような構文となっているかを理解するのが難しいときがあります。そのときに、省略された構文を再現できないと、なんとなく翻訳してしまう。それが正反対の意味で訳してしまうことがあるため、要注意といいます。
このように、英文での否定の構文における省略は、極めて合理的な思考。同じことを何度も繰り返すことはしないのです。同じなら省略する。同じでないところだけ残すのです。
なるほど~と関心していたときに、「これ、法律の条文と同じだ」とピンと来ました。会社法でも税法でも、同じ規定は何度も繰り返さない。第○条を参照させたり、準用させたりと、くどくどと規定文を置かないのです。
使い慣れていないと、この条文の使い方に戸惑います。あちらこちらの規定に飛ばされてしまうため、途中で見失いかねないから。ようやく辿り着くと、「なんだ、そんなことか。だったら、同じように規定しておいてよ」と思ってしまうほど。
ね、英文の否定における運用と同じじゃありませんか。だから、英語ができる人は条文が読める、あるいは、条文が読める人は英語が読める。そんな風に、ひらめいたのです。
とはいえ、誰もが最初から、こうした運用ができるワケでもない。だから、ボクは会計の実務解説書を書くときには、局面ごとに解説をしていきます。第○章を参照だったり、○と同様だったりとは説明しない。その箇所を読めば、他のページに飛ばなくても理解できるように本を作っています。
その代表例が、『税効果会計における 繰延税金資産の回収可能性の実務〈全面改訂版〉』(中央経済社)。企業の分類ごとに、他のページを参照させることなく解説しています。だから、繰延税金資産の回収可能性の判断に慣れている人には冗長に映るかもしれません。その代わり、不慣れな方にとっては、理解がしやすいハズ。
この本の発売が、2016年3月。もう、4年近くにもなるのですね。あの当時は、繰延税金資産の回収可能性に関して、JICPAの66号からの違いに気づいていない人が多いだろうと推測していました。だから、繰延税金資産の回収可能性の解説本への需要もそう高くはないと見込んでいました。
しかし、2,3年経ったときに、企業の分類の変更を検討する際に、はたと「66号と違くない?」と気づく人が増えてくるだろう。そのときに手にする本として成立することを意識して書きました。だから、変更時点にフォーカスした内容にはしなかったのです。
なので、そろそろ、この本の意図が伝わる時期になってきました。ASBJの規定以上の解釈を存分に盛り込んだ内容になっていますので、決算を迎える前に、一度、ご確認ください。あれ、いつの間にか宣伝になっている。たまには良いよね。