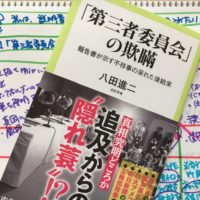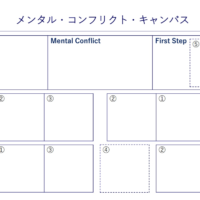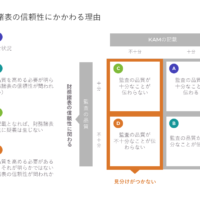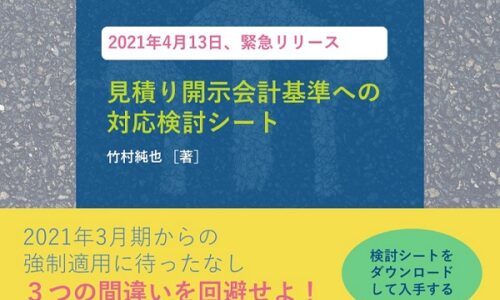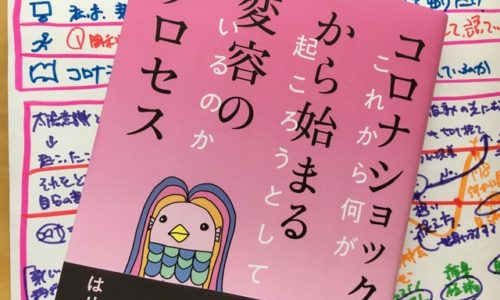学生の頃のボクは、作文が大の苦手。規定の文字数を超えた試しがない。なんとかして行を稼ごうとして、無理に文章を長くすることで2文字だけ改行されるようにしたり、同じフレーズを意味もなく何度も繰り返したりと。
それが今では、単行本も何冊も書いています。専門誌にも寄稿しています。あの頃に戻って、「大人になったら、本を出しているよ」と伝えても、絶対に信じてもらえないでしょう。
それほどまでに変化できたのは、ライティングの仕方を学んだから。
多くの人はライティングについて学んだ経験がありません。入試や資格試験の受験テクニックを身につけることができた人は良いのですが、多くの人は学生時代の国語や現代文の授業止まりのハズ。
簡単にいうと、まず素材を集め、次に構成を組み立てたうえで、最後に文章を書き出す。ライティングに着手する前に準備が必要なのです。これをなくして長い文章は書けません。
文章を書くときに、文字数に制限がある場合があります。何ページ内に収めるとか、何文字程度とするとか。紙媒体で掲載される場合には、物理的に紙面の制約があるからです。
出版社や編集者が予定したページを僅かでも超えると、中央での折り曲げを考慮して4ページ増える。ほんの数行オーバーした原稿を送りつけると、ほぼ4ページを他の何かで埋めなければならない。だから、仕事として執筆を行うには、制約を守ることがとても大切なんです。
とはいえ、一発目のライティングから規定の文字数に収めようとするのは無理。ベテランさんだとそれもできるのかもしれませんが、文章を書きながら文字数を収めることを気にしては執筆に集中できません。
だから、文字数制限を気にすることなく、頭の中のものを一気に書き出すのが良い。イメージした内容を発散していくような感じで。バァーっと、とにかくライティングを進めていく。誤字を気にすることもなく、正式名称も調べることもなく。
で、すべて書き出したら、その次は広げた内容を収束していく。推敲を通じて、必要なものだけに削り上げていくのです。
もちろん、必要だと思ってライティングした文章。決して無駄なものではありません。しかし、文字数制限がある以上、それに収めなければならない。本当に伝えたいメッセージに照らして、優先順位の低い文章を短くしたり、削ったりして調整していくことになります。
ちょうど今、抱えている専門誌への寄稿も、そう。今日の2020年5月30日、想定した執筆内容の9割以上が仕上がっています。この時点で、所定の文字数よりも10%程度オーバーしていました。でも、これは想定の範囲内のこと。ここから削っていきます。
ある段落をごっそりカットしていれば、文意が変わらない程度に途中の文章だけを削除してもいます。また、表現を工夫することで文字数を少なくしたところもあります。こうして、全体のバランスを踏まえながら、調整を加えていきました。
これによって、よりシンプルにメッセージが伝わるようになった感覚が得られましたよ。ライティングしているときは必要と思って書いた内容でも、まだまだ削れる余地があるものだと実感しました。
もし、専門的な内容について文章を書くチャンスがあるときには、その執筆は多めに書いたうえで削ることをオススメします。結果、文章をシュッとさせることができますから。学生の作文のように、無理くり文字を埋めているようでは、お金をもらう文章にはなりませんからね。