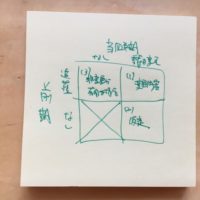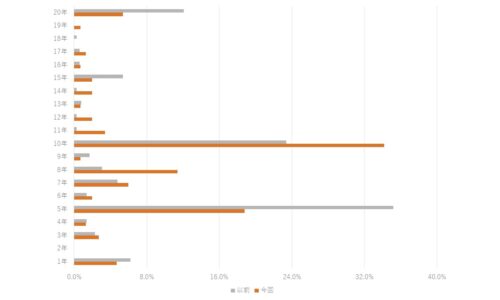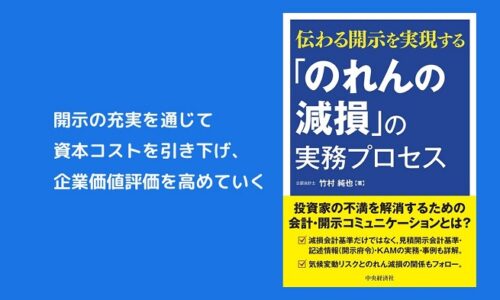何事も表面をなぞったモノマネじゃダメ。真似ることは何も悪くありません。それで上達するなら、どんどん真似たほうが良い。ただし、本質まで理解する必要があります。
先日、大学受験予備校が、今年の受験状況を解説する機会がありました。Zoomを使ったオンラインでのライブ配信。ま、最後には講座を勧める、いわゆる営業です。
しゃべりにこなれた男性が終始、解説を行っていきます。この人を「解説クン」と呼ぶことにしましょう。どこかのタレントのように、淀みなく次から次へと言葉が流れていく。
解説クンは、ときどき、「~な人は?」「~と考えている人は?」と受講している人に向かって呼びかけます。受講者は、それに向かって手を挙げたり、声を出したりと反応していく。こうして巻き込み型のファシリテートを繰り出していきます。
ボクはボクで、ファシリテーションを実践しているため、どんな技を繰り出しているのかがわかります。おそらく、解説クンは、リアルの場でも数多くの解説営業を行ってきたのでしょう。非常に慣れた感じで、受講者を巻き込もうとしている。
ところが、形だけを真似ているため、受講者としてはやらされ感が強い。確かに、手を挙げさせる、発表させるファシリテーションは、その場に巻き込ませるには効果があるもの。ただ、その後に感謝の言葉を添えないと、操作されている印象が生まれてしまいます。
解説クンは、感謝の言葉を添えることなく、淡々と進行していきます。おそらく、この巻き込み型ファシリテーションが良いと聞いたか学んだかして、リアルの場で実践してきたのでしょう。
リアルの場では、他の受講生と同じように振る舞わないといけないようなプレッシャーがかかるため、解説クンのようなレベル感でのファシリテーションでも通用していたと推察されます。たとえ、感謝の言葉がなくても、その場の雰囲気で乗り切っていたのかもしれません。
ただ、オンラインでは、他の受講生の様子がわからないため、同調圧力がかかりにくいのです。同じ効果を得るなら、リアルの場とは違う仕掛けが必要になります。
このように、形だけ真似て本質を見失うと、いざ、違う環境になったときに効果が薄れてしまいます。オンラインでは、リアルの場での技が同じように通用するとは限らないのです。
オンラインでの解説やセミナーで注意すべきは、リアルの場と同じようにファシリテーションできない局面があること。というのも、受講する身としては、リアルの場に行っているというよりも、自宅に解説の場が来ている感覚のほうが強いから。
実際、ボク自身が受講者となった体験としても、そう。新型コロナウイルスの外出自粛の期間に、他の方のオンラインセミナーを受けて実感したこと。
講師をよく知っている、他の受講生もよく知っているという環境ではない限り、リアルの場での巻き込み型ファシリテーションは、自宅でオンライン受講していると、どうも白けてしまうのです。
今回の予備校の解説クンは、オンラインであるにもかかわらず、早々とリアルの場と同じような進行していった。ボクの気持ちは白けたまま。だから、解説クンのファシリテートの粗さに目が行ってしまう。
「ああ、自己紹介の順番が早い」「あらかじめ何をするかを示さないと」「もっと上手なクロージングの持って行き方があるのに」など、気になる、気になる。若手や中堅のお笑い芸人にダメ出しする明石家さんまサンの気持ちがよくわかりましたよ。
見様見真似じゃなくて、きちんと学んだうえで実践することが大切。そうじゃないと、学習になりませんからね。学習にならなければ、その場しのぎとなるため、上達できないまま。
オンラインになっても、まだ、そのファシリテートを繰り返しますか。