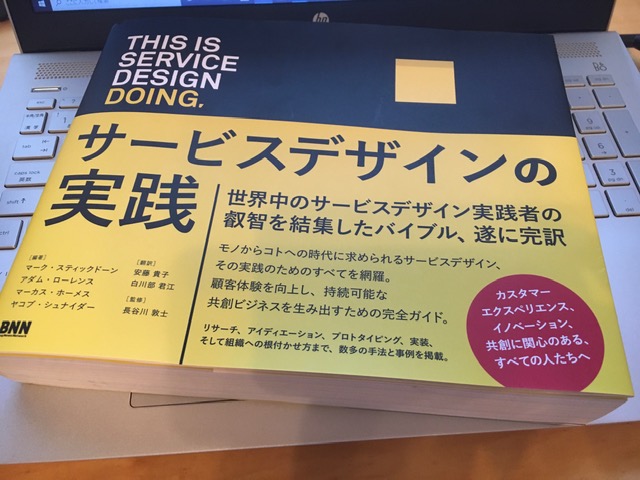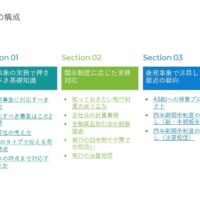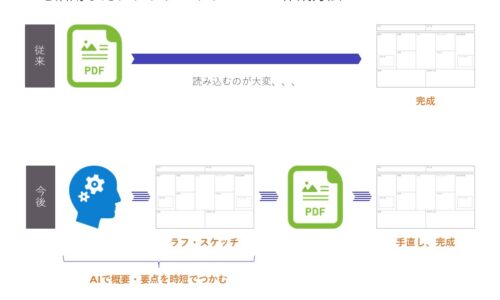収益認識の新基準について、「とっつきにくい」という声を聞くことがあります。基準に書かれている用語が難しいために、イメージが沸かないのです。
代表的なのは、「履行義務の充足」という用語ですね。義務を「充足」していくって、一体、どういうことでしょうか。頭の上に、はてなマークが100万個浮かんでしまいます。
義務の「充足」が理解できない理由
ボクも最近までは、そう考えていました。ワケのわからない用語でユーザーを混乱させるんじゃないと怒り気味で、収益認識の新基準を読んでいました。
しかし、「サービスデザイン」という領域に触れたときに、履行義務を「充足」していくことが身を持って感じ取れるようになれたのです。
先日、サービスデザインのセミナーを受講していたときに、「サービス・ドミナント・ロジック」と「グッズ・ドミナント・ロジック」という2つの概念を知りました。これらを聞いた瞬間に「充足」を理解できなかったのは、自分自身に原因があることを痛感したのです。
会計とは何も関係がない概念ではあります。とはいえ、そもそも会計とは、ビジネスを財務数値で表現するためのツールです。そのビジネスをめぐる環境が変わっていることを言語化できていなければ、会計を理解することができないのも事実。その言語化が、2つの概念だったのです。
サービスデザインとは
2つの概念を説明する前に、サービスデザインについて整理していきます。おそらく一番分かりやすいのは、2020年4月20日に経済産業省から公表された資料「サービスデザインをはじめるために―サービスイノベーションを加速するサービスデザイン入門」だと考えています。
それによると、サービスデザインとは「顧客にとって望ましい連続的な“体験”を提供するための仕組みとして“サービス”を構想し、実現するための方法論」だと説明します。顧客にとってより良い体験ができるための一連の体験だといえます。
「モノ」から「コト」(体験)へという表現を聞いたこともあるでしょう。かつてはモノが不足していたため、モノ自体に価値がありました。モノを引き渡すことで価値が交換できたのです。こうした考え方を「グッズ・ドミナント・ロジック」と呼びます。
やがてモノが溢れると、モノが売れなくなります。モノに価値があるなら、売れないことはないはずです。そこで、モノやコトをめぐるサービス全体を体験してこそ価値が生じると考えるようになります。こうした考え方を「サービス・ドミナント・ロジック」と呼びます。
売上計上における「引渡し」
この2つの概念がこうして言語化されると、従来の会計が基づいていた売上計上の最大の要件「引渡し」は、グッズ・ドミナント・ロジックに合致していることが理解できます。
企業が仕入れたり製造したりしたモノに価値があるため、それを引き渡すことが価値の交換だと考えることができるのです。そこには「充足」していくイメージが入り込みません。
これは財に限らず、用役という意味でのサービスも同様です。財と対比されるサービス(用役)のことを、ここでは狭義のサービスと呼ぶこととします。
狭義のサービスに価値があると考えると、それを提供したことをもって価値を交換したと考えることができます。これに基づけば、期間に応じて、あるいは、検収をもってサービスに関する売上を計上します。やはり、サービスを引き渡したことが重要な要件となります。
高級レストランのテイクアウトの悲劇
一方で、今のビジネスでは、サービス・ドミナント・ロジックで考えるほうがマッチしているものが増えてきました。これについて、最近、ボクが感じた事例を紹介します。
例えば、高級なレストランのテイクアウト。新型コロナウイルスによって来店が難しくなったため、テイクアウトを始めた飲食店が少なくありません。街の大衆的な飲食店も、ちょっと高級なレストランもこぞってテイクアウトを始め出しました。
高級なレストランでは、ある料理について店内で4,000円の料理を出していました。この料理をテイクアウトで販売するときに、同じ4,000円で販売したのです。これ、あなたは満足しますか。
ボクはそのニュースを見ていて満足はしませんでした。なぜなら、高級なレストランでは、料理というモノだけに価値があるからではありません。器だったり、接客サービスだったり、内装や照明といった空間だったりに価値を感じているからこそ、それらのサービス全体に4,000円という対価を支払うのです。
それが、大衆的な飲食店のテイクアウトと変わらない容器で提供され、情報提供というサービスも空間という雰囲気もなく、同じ料理だからといって同じ値段で設定している。これでは顧客の期待に応えられません。
広義のサービスに価値がある
高級レストランのテイクアウトという事例で考えたときに、料理だけに価値があるのではなく、それを取り巻くサービス全体に価値があることが理解できます。ここでのサービスという用語は、財と対比される用役ではなく、財や用役も含んだ広義のサービスとして使っています。
モノや狭義のサービスを渡すことで価値が交換されるのではなく、広義のサービスの一連の体験をひとつひとつ満たしていくことで、はじめて顧客が期待するサービスが提供できるのです。提供者側からいえば、履行義務の充足です。
このように、サービス・ドミナント・ロジックという概念がわかると、履行義務の「充足」のニュアンスが理解できます。価値とはさまざまな活動を通じて動的に生成されると考えると、「充足」していく様子がリアルに感じ取れるのです。
反対にいえば、グッズ・ドミナント・ロジックのビジネスに留まっている会社だと、履行義務の充足という意味を永遠に理解できないかもしれません。たとえ以前から同じ財やサービスを扱っていたとしても、そのビジネスがサービス・ドミナント・ロジックに移行することはできます。そういう移行に追いついていないと、引渡しの概念から抜け出すのは難しいでしょう。
これは私見です
もっとも、収益認識の新基準、つまりは、IFRS第15号で「履行義務の充足」という用語が用いられた理由がサービスデザインにあるとは、どこにも示されていません。ビジネスがそうシフトしているから、その現状にボクが勝手に当てはめただけ。ただ、それで納得できるなら何も問題がない。
ちなみに、この2つの概念は、マーケティングを専門とするスティーブン・バーゴとロバート・ラッシュ両教授が2004年に提唱したもの。一方、IASBとFASBによる収益認識共同プロジェクトが開始されたのは2002年のため、影響を受けていないと反論があるかもしれません。
しかし、2004年よりも前にもサービス全体で価値が生じる実態はありました。ただ、その現象に名前が付けられていなかったために、それを共有できなかっただけです。そう考えると、収益認識共同プロジェクトが始まった頃にもビジネスの変化を踏まえた議論がなされていると考えることができます。
また、2008年までの目標に合意したのが2006年のため、確実にサービス・ドミナント・ロジックは言語化されています。その概念を踏まえて「充足」するという言葉が使われた可能性も否定できません。
な~んてトンデモ説はここまでにして、『This is Service Design Doing サービスデザインの実践』(ビー・エヌ・エヌ新社)を読み進めていきしょうかね。
P.S.
こちらの緊急レポートは、多くの方にご覧いただいております。無料で入手できますよ。
P.P.S.
こちらのE-Bookも、大した告知をしていないにもかかわらず、お手にとっていただいております。お役に立てば何よりです。