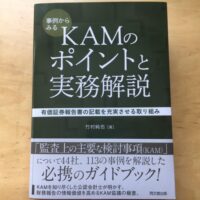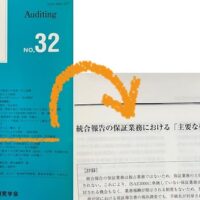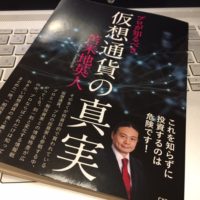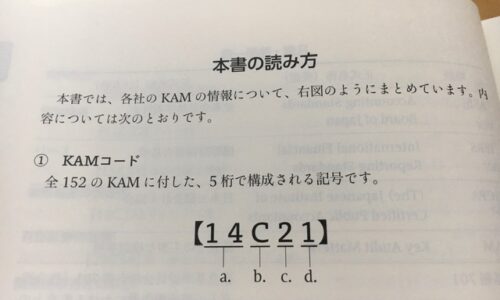シン・収益認識によって得られたものとは?
あっ、「シン・収益認識」とは、ボクの造語。新しく適用される収益認識の会計基準のことね。こう表現すると、「シン・ゴジラ」や「シン・ウルトラマン」のように、新しく、かつ、カッコいい感じがするため、気に入っています。それは、さておき。
このシン・収益認識は、3月末決算会社なら、2021年4月1日から始まる年度から適用されます。しかし、基準の言い回しが難しいためか、「わかりにくい」「読むほどに混乱してくる」「読んでも頭に入ってこない」「誰得なんだ」といった声も聞きます。
そこで、「シン・収益認識」と銘打って、基準の言葉をなぞるだけで終わらない解説を行ってみますね。
得られたものをシンプルに理解する
結論からいえば、シン・収益認識で得られたものとは、収益の認識の仕方。売上高の会計処理と言っても良い。それが、たったの2つに整理されました。
そもそも、「収益認識に関する会計基準」とは、会計基準と謳っているとおり、収益認識つまりは売上高をどう会計処理するかを整理したもの。ならば、売上について、どんな会計処理が求められるかを理解することが先決。
ここで、いわゆる5ステップをいきなり説明するのは野暮というもの。それはプロセスであって、ゴールではありません。ゴールは、売上高の会計処理。
もちろん、収益認識に関する注記も大きな目玉。以前のブログでも何度かお伝えしているように、売上高の会計処理が変わらなくても、注記は求められますからね。損益計算書のトップラインに関して何も情報提供されていない状況のほうが明らかにおかしいですから。
まちまちだった収益認識
シン・収益認識が登場するまでは、日本でも海外でも、売上高の会計処理に関して統一的な会計基準がありませんでした。
日本では「企業会計原則」で極めてシンプルな規定があるのみ。その他は税法の規定に準じて処理していたり、業種別の取扱いに基づいていたり、新しく登場した取引に対する会計処理の定めであったりと、まちまち。
海外も同じような状況でした。アメリカはあまりにも個々の収益認識に関する基準が多い一方で、IFRSはあまりにもシンプルなものしかありませんでした。
そこで、両者が収益認識の基準開発を行った結果が、IFRS第15号。それがほぼ翻訳される形で日本に導入されたのが、「収益認識に関する会計基準」です。
極めてシンプルなデザイン
こうしたシン・収益認識の会計基準によって、基準が適用される取引はすべて統一した取扱いとなるようにデザインされました。会計処理の観点から言えば、対象とされた取引は必ず2つの会計処理のいずれかが適用されることが明確になったのです。
すごくないですか、どんな取引も基本的には2つの会計処理のどちらかを選ぶだけなんですから。金融系の取引のように適用除外のものはあるものの、それ以外の取引は必ず2つの会計処理から1つが選択されるのです。めっちゃシンプル。
このシン・収益認識の基準によって、これからは、どんな業種だろうと、どんな新しい取引だろうと、適用対象となる取引であれば、必ず2つの会計処理のどちらかが選ばれるのです。将来に生じる取引も含めて、こんなに明確なルールはありません。予見可能性が高い、といえます。
もしも「基準が読みにくい」と感じているなら、シン・収益認識とは2つの会計処理のうちどちらかを決めることがゴールだ、と俯瞰して基準を眺めてください。この根っこを押さえられたら、あとは枝葉の話。もう楽勝です。
結論はたったの2つ
シン・収益認識によって売上高の会計処理は、たったの2つに整理されたとお話ししました。具体的には、次のとおり。
- 一時点で収益を認識する
- 一定の期間にわたって収益を認識する
このうち、一定の期間にわたって収益を認識していく方法にはいくつかのパターンがあります。とはいえ、基本的には、この2つから選択していきます。
このように、どんな取引もたった2つの会計処理に整理されたことが、シン・収益認識の最大の功績。これによって業種別の会計の定めやこれから新しく登場する取引についての会計の定めも不要になりました。
で、この2つのいずれかを選ぶか。そこで出てくるプロセスが、いわゆる5ステップです。これはあくまでもゴールを導くためのプロセスに過ぎません。ゴールを知ることなくプロセスに走っては、基準の迷路にハマるだけ。
でも、もう大丈夫。この話を聞いて、その迷路から抜け出せましたから。
基準が迷路であるもうひとつの理由
今、「迷路」と表現したのには、プロセスとゴールでお話ししたこととは別の意味があります。それは、IFRS第15号の開発の過程でのこと。
一時点で収益を認識する方向で動いていた時期がありました。それだと、長期の請負工事やソフトウェア開発でも、いわゆる「完成基準」しか使えなくなります。それでは事業活動の実態を表せなくなるとの批判がありました。そりゃ、そうですよね。
そこで、いわゆる「進行基準」的な会計処理も認められるように検討が進められた結果、一時点だけではなく一定の期間にわたっても収益を認識することが可能となりました。
このとき、一定の期間にわたって収益を認識していくにあたって、あの「履行義務」という考え方が取り入れられました。それが基準を読み取りにくくさせた原因のひとつ。基準を丁寧に詳しく読み取る人ほど混乱してしまう理由がここにあるのです。
この辺り、辻山栄子先生の論文「新収益認識基準と会計基準国際化の功罪」『Accounting(企業会計) 2020年4月号』に詳しいので、ご興味のある方は、ぜひ、ご覧ください。


で、この後は何をする?
さて、シン・収益認識とは、たった2つの売上高の会計処理のどちらかを選ぶことだと説明してきました。このシンプルなデザインを明確に指摘する解説にお目にかかったことがあるでしょうか。
もしかすると、「なんだ、それだけのこと?」と拍子抜けされたかもしれません。
その答えは、半分イエスで、半分ノー。確かに、収益の「認識」としては、これだけ。
もちろん、今まで収益を一時点で認識していたものが、一定の期間にわたって認識していくことに変わるケースもあるでしょう。その反対のケースもあるかもしれません。いずれにせよ、この2つの選択以外にはありません。それくらいにシンプルなんです。
しかし、「収益を認識する対象は何か」「その金額はいくらか」という点に注目すると、従来の会計処理から変わるケースがあります。その結果、売上高が想定した時期に想定した金額で計上されなくなる可能性があります。
それが利益インパクトにもなるのですが・・・、それはまた、別の話。
P.S.
続きが聞きたくなったら、SNS上で「続きを求む」と声を聞かせてください。ハッシュタグは、「#シン・収益認識」。
P.P.S.
実務的な対応にご興味があるなら、こちらをどうぞ。もちろん、ダウンロードするかどうかは、あなた次第。