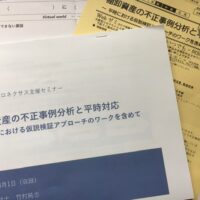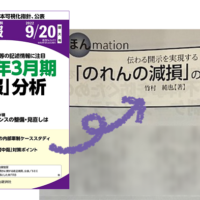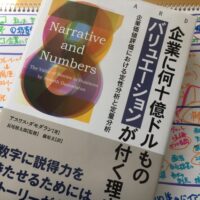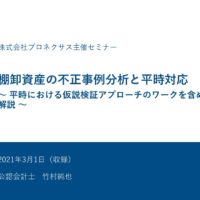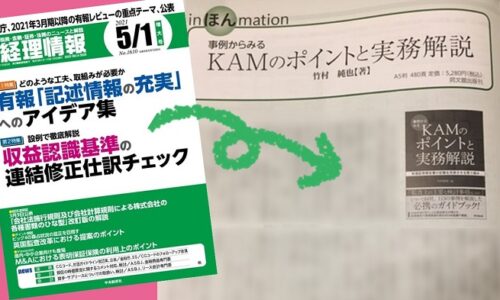こんにちは、企業のKAM対応のスペシャリスト、竹村純也です。
KAM(監査上の主要な検討事項)といえば、記述情報と深い関係があります。KAMに未公表の情報が記載されるときに、関連する情報を記述情報で対応することがあるから。
そんな記述情報は、2020年3月期からの有価証券報告書で、充実を図る改正が行われたばかり。上場企業は記述情報をいかに充実させるべきかを検討しているハズ。
しかし、ある企業の方はこう、おっしゃいます。「ウチの会社は、好事例集に掲載されるような大きな会社じゃないから」と。つまり、中小規模のため、記載することがそんなにないと考えるのです。
これ、誤解です。
誤解の元を辿ると・・・
ただ、誤解を招きかねないことに気づきました。それは、「充実」という言葉。
記述情報の充実と言われると、今まで以上に記載が求められるような印象を与えかねない。ちょうど、KAMに関連して、「追加」の開示が必要になる、なんて話もあったため、つい記載を増やすことだと捉えてしまいます。
しかし、「充実」という言葉が意味する内容とは、十分に備わっていたり、中身が満ちていて豊かであったりと、内面のこと。ボリュームのことではないのです。
もちろん、十分な記載とするためには、相応のボリュームが必要になることもあります。ただ、その場合でもボリューム増は、副次的な作用にすぎません。その本質は、内面を満たすこと。
制度趣旨に立ち返る
記述情報の充実という改正も、記載のボリュームを問うているのではありません。そこに記載される内容が十分なのかが問われています。
改正の目的は、企業と投資家との建設的な対話をより促進させること。どの企業も書いているような内容やレベル感では、建設的な対話の前に、企業の状況を確認しなければならない。そうならないような記載が求められているのです。
会社名を隠して記述情報を出したときに、その企業だと理解できるくらいの内容が良い。どの企業でも使い回しできるような、そんな紋切り型の記述では、改正の趣旨に沿っていません。
監査人もKAMで悩んでいる
紋切り型の記載ではいけないには、KAMも同じ。KAMも、どの企業にも使い回しできるようなボイラープレートではない記載とするよう、注意喚起されています。
なぜなら、KAMの本来の目的は、財務諸表監査に固有の情報を記載することだから。企業のリスクをさらけ出すことが第一の目的ではありません。結果的にそうなる状況もあるかもしれませんが、それを開示することが制度趣旨ではない。
あくまでも、財務諸表監査に固有の情報を記載することが、KAMの目的です。
すると、記述情報の「充実」とは、企業の固有の情報を開示することに他ならないことが理解できます。企業が取り組んでいること、降り掛かっていること、障害となることなどを記載していく。どんな活動を行っているか、それに基づき記述情報を作成していくのです。
ちょっとした一言の違い
記述情報の充実とは企業の固有の情報を開示すること。そう理解するなら、「ウチの会社はそんな大規模じゃないから」という考えは浮かんでこないはず。企業の規模に関係なく、現実に取り組んでいる活動があるから。
そういう意味では、記述情報の「充実」という言い方よりも、記述情報に「固有の情報を書く」という表現のほうが正確かもしれません。ちょっとした一言の違いで、受け取る印象が大きく変わります。
とはいえ、企業に固有の情報を記載するためには、活動を言語化するためのスキルが必要です。文字を書くというライティングであったり、何をどう書くかという編集であったりと、テキスト化していくための能力が欠かせません。
もし、言語化にお悩みなら、ボクがお手伝いできます。単著も寄稿も数多く手掛けているため、自分自身の活動として言語化することを十年以上行ってきました。
言語化するアドバイスやサポートをお求めなら、一度、お声がけください。すでに、記述情報の充実に関するコンサルティングを実施しています。