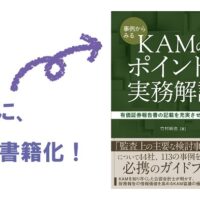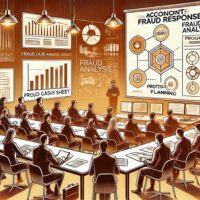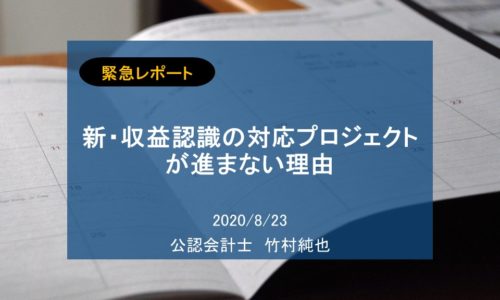「企業が注記を充実してくれないから、KAMが書きにくい・・・」
そんな話が、会計士サイドから発言されました。それは、今日の2022年3月31日に開催された、JICPAによる研修会「日本証券アナリスト協会『証券アナリストに役立つ監査上の主要な検討事項(KAM)の好事例集』に関する投資家と監査人の意見交換」でのこと。アナリスト側から、充実していないKAMがあるとの指摘を受けて、冒頭のように返答していたのです。
この返答の背景には、KAMの問題ではなく、財務諸表監査の品質の問題があると考えています。というのも、財務諸表監査がリスクアプローチではなく、科目アプローチになっている可能性があるからです。
確かに、特定の科目について説明する場合には、それに関する注記が財務諸表になければ、KAMに記載することが困難な状況が想定されます。監査人が一次情報の提供を避けるためにも、財務諸表にKAMに記載する内容が注記されていて欲しい。そういう考えに至ると、冒頭の発言につながります。
しかし、財務諸表監査は、科目アプローチではなく、リスクアプローチによって実施するもの。そこでいう「リスク」とは、事業リスクから導かれた、財務諸表の虚偽表示リスクです。
では、事業リスクは何から生じるか。
この点を押さえていないため、結果的に科目アプローチに陥っているのです。財務諸表監査の実施が科目アプローチなら、KAMの記載も科目アプローチにならざるを得ません。すると、それを説明するための内容が財務諸表に開示されていなければ、という論法になります。
リスクアプローチの下での事業リスクは、ビジネスモデルが理解できていなければ、適切かつ的確に識別することはできません。ビジネスモデルがあるからこそ、経営戦略が導かれ、また、事業環境の変化に影響を受けるのです。こうした中で、事業リスクが自ずと導かれるのです。
事業リスクとは、決して、たまたま思いつくものでもなければ、他社の開示を借用するものでもありません。ビジネスモデルの各要素と密接に関連しているものです。そういった事業リスクが識別されなければ、リスクアプローチを実施することはできず、また、期待されるKAMも書けません。ましてや、気候変動の影響を考慮した監査にたどり着くこともないでしょう。
反対に、事業リスクに着目したリスクアプローチによれば、KAMとされたリスクが導かれる材料は、まさしく、ビジネスモデルや経営戦略、事業環境の変化など。これらは、財務諸表以外の箇所で開示されています。有価証券報告書の記述情報や会社法の事業報告はもちろんのこと、コーポレートガバナンス報告書に開示されるものもあります。
これらは、たとえ注記されていなくても、注記以外で開示されているため、周知の事実。よって、KAMに書けないことはありません。ついテクニカルな部分に走りがちな気持ちを押さえて、もともとのリスク評価の手順を丁寧に説明するほうが、アナリストをはじめとした財務諸表の利用者に対する説明として適切かつ効果的でしょう。
気をつけたいのは、ビジネスモデルとは単なる商流ではない点です。「この会社は、コレを仕入れて、アレを売っている」という程度では、ビジネスモデルとはいえません。それでは、同じものを扱っている企業のビジネスモデルはすべて同じになってしまいます。そんなことはありません。
例えば、同じハンバーガーを販売していても、マクドナルドとモスバーガーではビジネスモデルが違います。商流だけでは両社の違いが区別できないため、事業リスクも表面的な識別にとどまります。それでは、経営者とのディスカッションや監査役等とのコミュニケーションも、貧弱なものになるのは目に見えています。
もっとも、監査チームが科目アプローチ的になってしまう原因のひとつに、協会レビューや金融庁検査の影響があるかもしれません。これらの中で、KAMとなるほどに重要なリスクの識別とその対応を掘り下げていくのならよいのですが、もしも、実施された監査手続をどれも等しくチェックしていくようなら、事業リスクに基づくリスク評価よりも、リスク対応手続に関心を向けるような誘導となりかねないためです。
いまいまのレビューや検査の状況はわかりませんが、せっかくKAM制度が導入されたのだから、特に重要と判断したリスクは何か、また、それに対する手続はリスクに直接対応した効果的なものかどうか、という点に絞り込むような方法が適していると考えます。さらにいえば、監査の好事例集といったものがあれば、なお良いかと。会計士は誰もが、ちゃんとした監査を実施したいと考えていますから。
P.S.
KAMについて分析した結果は、拙著『事例からみるKAMのポイントと実務解説』にてご覧いただけます。まずは、こちらの紹介ページをご確認ください。