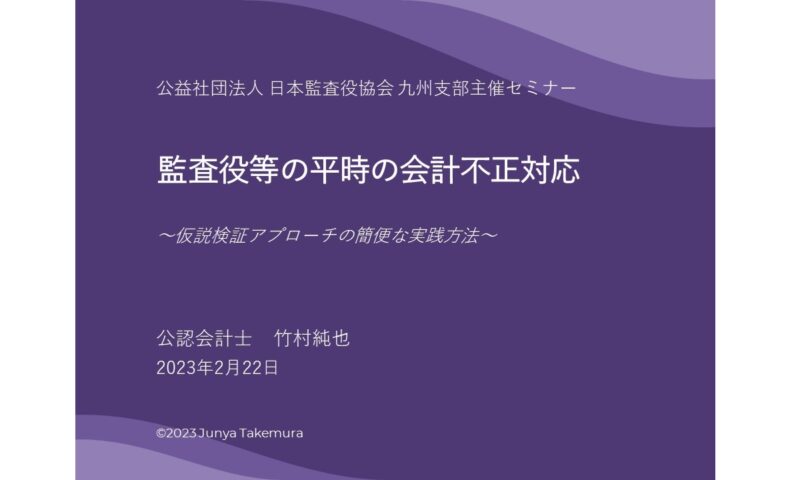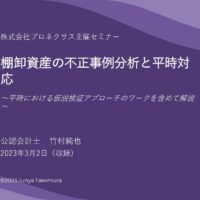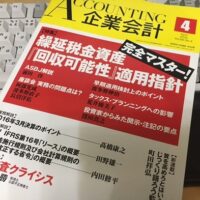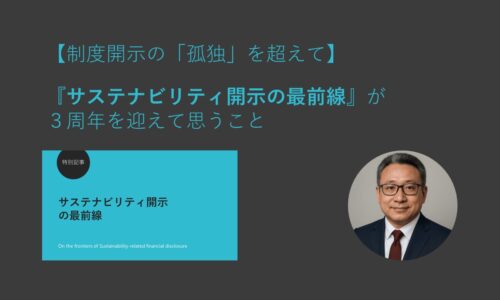2023年2月22日(水)、九州は博多で、日本監査役協会の九州支部が主催するセミナーの講師を務めてきました。以前にブログ記事でお話ししていたセミナー「監査役等の平時の会計不正対応」です。
このセミナーは、現地の会場に参加することもできれば、ライブ配信を視聴することもできる、いわゆるハイブリッド型で開催されました。そのおかげもあるのでしょう、実に多くの方々にご参加いただきました。それゆえに、悔しかった点と嬉しかった点がありました。これらについてシェアしますね。
■悔しいのは、花粉症
講師として、この時期に気をつけたいのは、花粉症。声やのどに支障が出ては、仕事になりませんからね。そこで、万全の体調で向かうために対策を取っていました。しかし、2日前の夜に、急激に悪化。苦しいよりは、痛恨の極み。悔しいったらありゃしない。
直前まで応急の処置を施したものの、さすがに何事もなかったかのような話し方までは回復しませんでした。途中、鼻水は流れるわ、せきも出るわで、さぞかし聞き苦しかったハズ。それにもかかわらず、セミナーの終了時に皆さんから、大きな拍手をいただきました。温かい方々に、また、事務局の方々に救われました。この場を借りて御礼申し上げます。
セミナー内容は、事務局サイドからのリクエストも踏まえながら、ゼロベースで作り上げたものでした。もちろん、著書やセミナーからの素材は用いているものの、全体的な構成は今回のセミナーにあたって大きく見直したものです。受講者が監査役に限定されていたため、対象者が明確に絞り込まれていたことも功を奏しました。
■仮説検証アプローチのクイックバージョン2.0の効果
その効果が特に大きかったのは、本邦初披露の「仮説検証アプローチのクイックバージョン2.0」でした。従来の様式をより使いやすいように改定したものです。これを記入していくワークを通じて、不正発見のための、しかも平時における仮説検証アプローチの検証手続を立案していきました。
様式に加えて、説明用のスライドも一新しましたよ。手順のみならず、記入のためのヒントも盛り込みながら、作成の障害となるような要因を取り除きました。ワークをしているときに、皆さん、ペンがすらすらと動いていたため、きっと効果があったのでしょう。
ワークの時間は、手順の解説も含めて15分程度。そんな短時間で、手元のシートに、仮説検証アプローチの検証手続が出来上がっていることを体験できた様子でした。「実務に適用できる自信がワークを行う前と比較して高まった方もいらっしゃるでしょう」と尋ねたときに、大きく頷いた受講者の表情が印象に残っています。
■反響のあったフラウド・キャンバス
セミナー終了後に問い合わせがあったのは、不正事例を紹介したときに、まとめシートとして示した「フラウド・キャンバス」です。これは、不正事例のポイントを的確に押さえるために開発した紙一枚のツールです。「ビジネスモデル・キャンバス」のように、複数の要素を有機的に関連していることが一望できます。
元々は、セミナー準備のために活用していたツールでした。あるとき、「これをそのまま紹介したほうが不正事例の概要を理解しやすいのでは」と思いついたため、セミナーでも説明するようにしています。今回のセミナーでは、フラウド・キャンバスにおいて、不正事例に関する9つの要素がどう有機的に関連しているかを図解したスライドも追加しました。
それが、今回、「このツールを活用したい」との連絡を受けたのです。セミナーを受講して終わりではなく、こうして持続的な学習につながったことは、講師として嬉しいですね。花粉症で聞きにくいセミナーでありながらも、コンテンツはしっかりと届いたようです。
■フラウド・キャンバス作成の効果的な方法
フラウド・キャンバスの作成にもニーズがあることが、今回のセミナーで得たもののひとつでしたね。これを作成できるようになる最も効果的な方法は、ワークショップ形式のセミナーでしょう。自転車の運転のように、実際に体験していくことが最短の近道。
例えば、不正事例を特定したうえで、事前に作成したフラウド・キャンバスを発表しあう方法もあるでしょう。事例によっては、着眼点が変わると、フラウド・キャンバスの描き方も変わることが理解できますからね。
その他に、自身が理解したい調査報告書を選んでおいて、当日、作成のためのエッセンスを短時間でつかんでいく方法もあります。以前、会計士向けに企画していたところ、コロナ禍に入ったため、開催できなかったものです。
それよりは、多くの不正事例を解説したうえで、フラウド・キャンバスの作成方法を解説した書籍のほうが、必要とされる方に届きやすいのかしら。書籍を通じて数稽古を疑似体験していくイメージ。まだ、セミナーでしか紹介していないツールですからね。
ま、いずれにせよ、お声がかかってからの話。