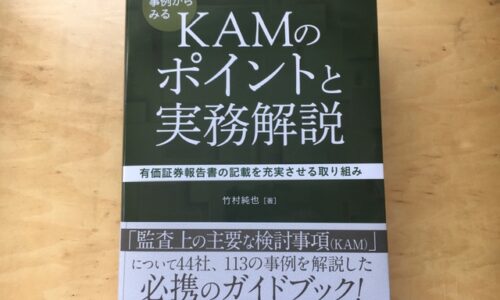ISSBのS1基準では、サステナビリティ開示を行う手順が定められています。日本でもSSBJがこれに基づき日本版S1基準を設定していくため、近い将来の有価証券報告書におけるサステナビリティ開示も同じ手順で行っていくものと見込まれます。
そのISSB基準で定められているサステナビリティ開示の手順は、次の2つです。
- 〔手順1〕「サステナビリティ関連のリスク及び機会」が何かを識別する。
- 〔手順2〕「サステナビリティ関連のリスク及び機会」に関する開示情報を識別する。
このうち〔手順1〕については、前回の記事「サステナビリティ関連のリスク及び機会の3つの識別プロセス」で説明したとおりです。
これらの手順における識別プロセスは概ね共通しているものの、追加された識別プロセスがあります。また、〔手順1〕で気候変動を識別した場合には、〔手順2〕ではS2基準「気候関連開示」に従う必要があります。規定を見るだけでは、その違いを理解しにくいこともあるでしょう。
そこで今回の記事では、〔手順2〕を解説していきます。特に気候変動を識別した場合に〔手順2〕で活用する「IFRS S2の実施に関する産業別ガイダンス」について、その辿り着き方を7ステップで整理しました。これによって、迷うことなく開示候補の検討が始められるようになります。