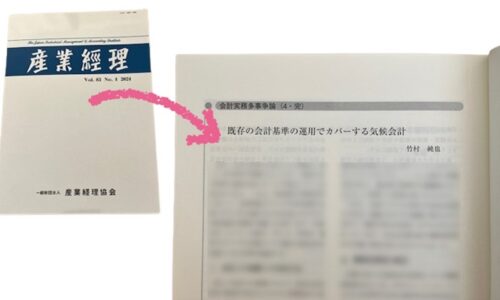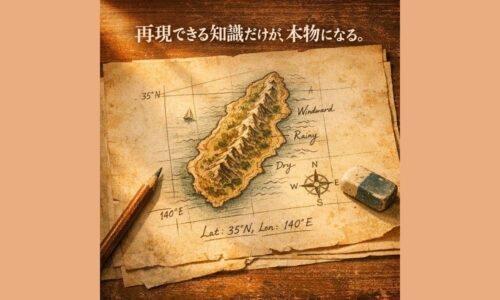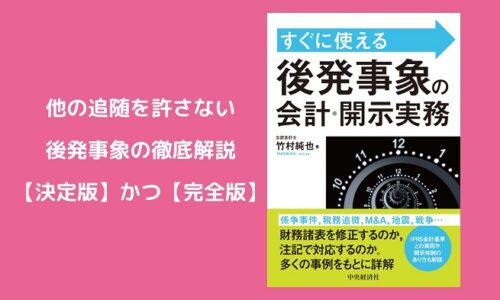近年、企業の財務報告における気候関連リスクの開示が世界的な課題となっています。その中でも、日本における監査制度の在り方が、気候リスクの適切な監査を妨げる要因の一つとして指摘されています。特に、監査期間の長期化が、監査報告書における気候関連開示に与える影響として懸念されています。
2025年3月、気候変動が金融市場に与える影響を調査するカーボントラッカーが、「フライング・ブラインド」シリーズの最新報告書を発表しました。本報告書では、各国の財務諸表や監査における気候関連開示の実態を分析するとともに、日本市場についても詳細に評価しています。その中で、日本の監査制度における監査継続年数の長さが、日本企業の監査における気候リスクの考慮を妨げる結果、透明性を損なう要因になっている可能性があるのです。
そこで、今回の特別記事では、カーボントラッカーの最新報告書について概要を整理しながら、日本市場に関する分析結果を詳細に解説します。その内容は、次のとおりです。
■「フライング・ブラインド」シリーズの最新報告書
■財務報告の気候開示格差が鮮明に
■気候開示強化に向けた規制当局への提言
■気候リスク開示「ゼロ」の衝撃! 日本企業の財務諸表に欠けているもの
■日本の監査報告書における気候情報開示の実態
■日本の規制当局の対応と課題
■監査ローテーションの影響:長期契約がもたらす課題と投資家の懸念
■この記事の3つの重要ポイント
この記事を読むことで、国際的な投資環境の中で日本企業が抱える課題を理解できるようになります。また、日本の監査報告書における気候リスクの開示が遅れている現状を知ることで、監査の透明性や信頼性を評価する視点を得られます。さらに、長期にわたる監査契約が企業と監査法人の関係を固定化する結果、気候リスクの開示に対する監査の厳格さを損なう可能性を認識できます。
この機会にぜひ購読し、限定コンテンツを通じて、より深い知識を身につけてください。あなたのビジネスの未来に直結する情報を常に先取りしましょう。