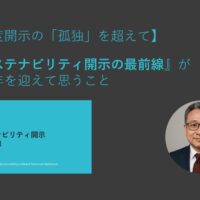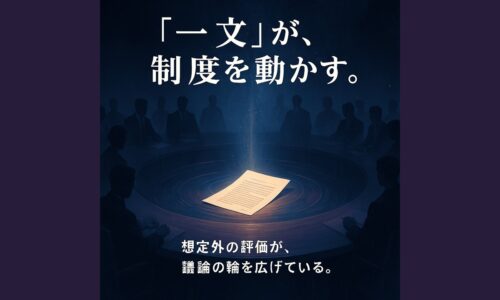■サステナビリティ開示基準を活用するための賢い方法
サステナビリティ基準委員会(SSBJ)は、2025年3月5日にサステナビリティ開示基準を公表した後、その導入支援策を次々と繰り出していますね。具体的には、3月27日に補足文書を、3月31日にはSSBJハンドブックを、さらに4月1日にはISSB基準との比較・対応表を公表しました。ISSB基準との整合性を強く意識する企業にとっても、ISSB基準やSSBJ基準の理解を深めたい企業にとっても、実務上、有益な資料になるでしょう。
ただし、その使い方には注意が必要です。なぜなら、これらの資料は、実務で利用する場合の方向性が反対だからです。まるで一方通行の標識のようなものですね。
これらの資料の活用は、どのような局面で行われるのでしょうか。それは、「そもそも、どのように解釈するものなのか」「具体的な適用はどうすれば良いのか」「うちの会社の対応は間違っていないか」と疑問に思ったり、心配になったりするときです。つまり、SSBJ基準の要求事項を目の前にしている局面なんです。そこでは、SSBJ基準を起点として関連する支援資料を探したいはずですよ。
しかし、これらの支援資料からはSSBJ基準に遡ることができても、SSBJ基準を起点として該当する支援資料があるかどうかは明確にはなっていません。基準の本文を見ても、「この補足文書が関連する」とか「あのSSBJハンドブックを参照できる」とは記載されていないからです。このように、支援資料からSSBJ基準への方向には道筋が確保されているのに対して、SSBJ基準から支援資料への方向には「容易」にたどり着けないのです。これって、迷路の出口は見えるけど入口が見つからない状態みたいですね。お気づきでしょうか。
もちろん、すべての支援資料を把握していれば、問題ないでしょう。とはいえ、遵守が求められない支援資料をひとつひとつ内容を確認していく作業は、限られたリソースを配分する観点からは合理的ではありません。その意味で「容易」ではないと表現したのです。
このような一方通行の構造には理由があります。その理由を支援資料の種類ごとに説明していきましょう。そして、この構造を解消するための「SSBJリンクマップ」もご提供いたします。