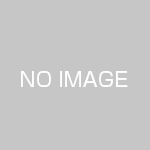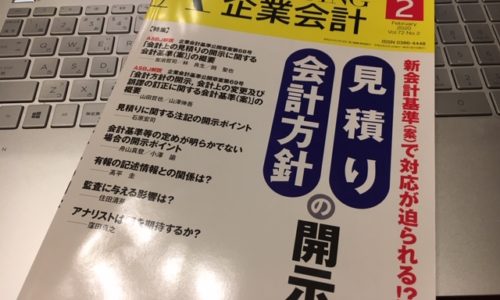2025年6月30日。夕闇が迫りつつある本社ビルの一室で、新リース導入プロジェクトのメンバーたちは、明日の監査法人との協議に向けた最後の準備を進めていた。霧坂美咲の指先が、ノートパソコンのキーボードの上で静かに踊る。彼女の表情は穏やかだったが、その瞳の奥には複雑な感情が揺れていた。退職を目前に控えた最後の仕事。それは彼女にとって、日本での集大成となるはずだった。
「霧坂のほう、大丈夫そうか?」
黒嶺尚吾の声には、わずかな心配が混じっていた。彼の眼鏡の奥の瞳が、真剣な光を宿している。
美咲は手元の資料から目を上げた。延長オプションに関する会社の判断方針を説明したものだ。明日の協議では、一般的な重要性の判断が受け入れられるためにも、通常の判断の適否が大きな論点となるのは容易に想像がついたからだ。
「大方のところは。あと少しだけ整理したいので」
彼女の声には疲れが混じっていた。それでも、仕事に対する責任感は少しも揺らいでいない。
「え~、残業? 本当だったら今頃は退職慰労会が始まってる頃じゃないですか」陽野沙織の声には、惜しむような響きがあった。彼女の目は、美咲を見る度に少し寂しそうになる。ともに過ごした時間が、もうすぐ終わってしまうことを実感していた。
「確かにね」美咲は微笑んだ。その笑顔には、どこか儚さが漂っていた。
「本部長が人事に無理を言って、本当に退職日が7月末になっちゃって。でも、明日はこの計算モデルをしっかり説明しないと」
「俺もプロジェクターの準備を済ませておくよ」誠人の声が慌ただしく響く。「この時間なら、誰も使わないから」
その言葉に込められた本当の意味を、誰も指摘しなかった。しかし、美咲は誠人の視線の奥に隠された思いに気づいていた。彼の言葉の裏側には、彼女と二人きりになりたいという欲求が見え隠れしている。そのことに気づいていながらも、美咲は敢えて触れないでいた。
「じゃあ、手の空いた順に帰ろう」黒嶺が立ち上がる。「そうだ、本部長が言ってた。明日は13時スタートだから、12時くらいに集まろうと」
黒嶺の背中が、会議室のドアの向こうに消えた。残された三人の間に、微妙な空気が流れる。美咲はノートパソコンに集中しようとしたが、誠人の視線を感じて、落ち着かなかった。
しばらくしてから、誠人が声をかけた。
「コンビニに行ってくるけど、何か要る?」
その声には、いつもの軽さがなかった。どこか緊張したものを感じる。
「私が行ってくる」美咲が即座に答える。「今日中にポイントを使っておきたいから」
その言葉に、改めて胸が締め付けられる。彼女の日常が、もうすぐ終わるのだ。そして、自分と誠人との間に確かにあった何かも。言葉にできなかった思い。それが美咲の胸の奥で、再び疼き始めた。
「夜島くんは肉まんでしょ。沙織はいつもの紅茶?」
美咲の問いかけに、二人は無言で頷いた。誠人の目には、何かを言いたげな光が宿っていた。しかし、彼は口を開かなかった。沙織は二人の様子を横目で見ながら、小さくため息をついた。
美咲が去った後、誠人はプロジェクターの調整に没頭していた。画面には、「『更新がないこと』の事前説明書に関する調査」という文字が映し出されている。彼の動きには、どこか焦りが感じられた。
沙織が「手伝う」と近づいてきた。
「これで完璧だ」誠人は満足げに呟く。
「一体、何してるんですか?」
沙織の声が、いつもと違う鋭さを帯びていた。彼女の瞳には、普段の明るさとは違う、真剣な光が灯っていた。
「見ればわかるだろ。今、微調整してて…」
「そんなことしてる場合じゃないでしょ!」
「位置は大事だろ。霧坂が、リース負債のグルーピング方針を説明するときに…」
「美咲先輩はもう明日で最後なんですよ。いいんですか、このままで?」
沙織の言葉が、会議室の空気を変えた。まるで、画面に映し出された会計基準の文字までが、冷たく光を放っていた。窓の外では、東京の夜景が次第に明るさを増していた。しかし、会議室の中の温度は、急激に下がったように感じられた。
「仕方ないだろう。霧坂が決めた道だ…」
「だったら、『霧坂、霧坂』って、いつまで未練がましくしてるんですか!」
「え?」
誠人は戸惑いを隠せない。いつもの陽気な沙織とは明らかに違う。彼が知らなかった沙織の一面が、突然現れたように感じた。
「どうしたんだよ」
近づいた誠人の目の前で、沙織は顔をそむけた。その頬を、涙が伝っていた。誠人はその涙に戸惑った。
「夜島さんは、肉まん食べてる『浅はかマン』じゃなくて、『無神経マン』よっ!」
突然の抱擁に、誠人は凍りついた。プロジェクターの光が、二人の影を壁に映し出す。その瞬間、沙織の行動の意味を理解しようとした。だが、理解する前に——。
「ただいま~」
会議室のドアが開く音と共に、美咲の声が響いた。そこには、抱き合う二人の姿があった。時間が止まったかのように感じられた。
「え…」
白い袋が、美咲の手からこぼれ落ちる。床に転がった肉まんが、静寂を破るように音を立てた。画面に映る「更新がないこと」の文字が、皮肉に輝いていた。「更新がない」——それは彼らの関係にも当てはまるのだろうか。
「あっ、ごめんなさい…」
かすかに震える声を絞り出して、美咲は走り去った。その背中には、言葉にならない感情が集約されていた。
時計の針が、ゆっくりと一時間を刻んでいく。会議室の両端で、誠人と沙織は黙り込んでいた。プロジェクターの光だけが、空しく壁を照らしている。誠人の頭の中は、美咲の驚きに満ちた表情で一杯だった。彼女の瞳に映った痛みが、自分の胸を締め付ける。
「美咲先輩にちゃんと告白してくださいね」
沙織の声が、突然会議室の沈黙を破った。
「えっ…」
「こんなの、挨拶。海外じゃ珍しくないから…」
沙織の声は、無理に平常を装っていた。先ほどの涙の痕跡が残っていたが、表情は一変していた。
「挨拶って…霧坂に見られたんだぞ!」
「私だって、後輩の仮面を被った泥棒猫でしょ」
誠人は言葉を失った。プロジェクターの光が、まるで二人を審判するかのように煌々と照らしている。彼は沙織の真意がわからず、混乱するばかりだった。
「とにかく美咲先輩に告白すること。明後日には日本から居なくなるんだからね」
そう言い残して、沙織の姿も消えた。彼女の足音が廊下に消えていくのを聞きながら、誠人は深いため息をついた。
誠人は何度も美咲に連絡を試みた。しかし、メッセージは既読にならず、電話もつながらない。彼の焦りが増していく。何とかして彼女に説明したい。誤解を解きたい。そして、言葉にできなかった本当の気持ちを伝えたい。
会議室の窓からは、東京の夜景が見えた。無数の光が、夜空に浮かぶ星のように輝いている。その一つ一つの光の向こうには、それぞれの人生が広がっている。美咲はどこにいるのだろう。彼女は今、何を思っているのだろう。
誠人は肉まんの袋を見つめた。もう冷めてしまっている。それはまるで、彼の中の情熱が冷めることを恐れているかのようだった。明日、彼女に会えるだろうか。そして、本当の気持ちを伝えられるだろうか。
結局、彼にできたことは、ゆっくりと会議室の明かりを消すことだけ。プロジェクターの電源を切ると、「更新がないこと」の文字も闇に消えていった。
床には、冷めた肉まんが転がったまま。それは、言葉にできなかった想いの象徴に見えた。誤解の夜が、静かに更けていく。
(第16話「開かないファイル」へ続く)