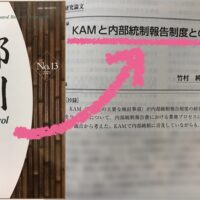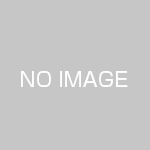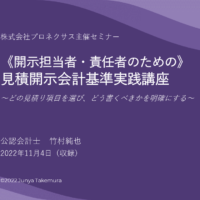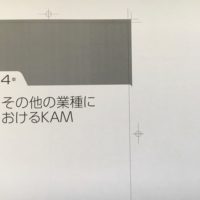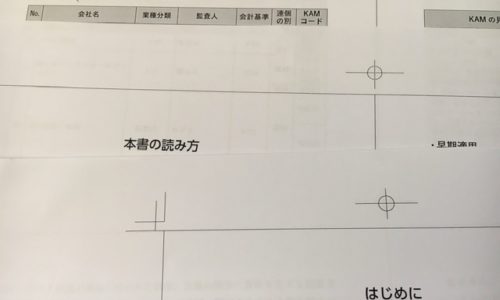2030年1月、夕闇が迫りつつあるグランドボールルームの窓辺に、霧坂美咲の姿が映り込んでいた。講演会が終わり、スタッフが片付けを始める中、彼女は遠い日の記憶に浸っていた。窓ガラスに映る自分の顔と背後の豪華なシャンデリアの光が重なり、まるで二つの時間が交錯するかのようだった。
「日本の会計実務に必要なのは、財務モデリングの専門家です」
自分の声が会場に響いていたのは、ほんの数十分前のことだった。「不動産賃貸借契約の資産計上額を算定するために、必要な情報を入力していた」あの日々が、まるで昨日のことのように蘇る。美咲は窓に手を当て、硝子越しに東京の夜景を眺めた。変わった場所もあれば、変わらない場所もある。人の心も同じなのだろうか。
5年前のあの日。誰にも告げずに去った自分は、果たして正しかったのだろうか。そのときの選択が、今の自分を作り上げたことは確かだ。だが時々、別の道を選んでいたら——という思いが頭をよぎることがある。
“Kiri, the next meeting starts in 30 minutes.”
コンサルティング・ファームの同僚の声に我に返った美咲は、エレベーターに向かって歩き出した。日本での講演を終え、次の予定に移る。それが今の彼女の日常だ。しかし、その歩みを止めたのは、1階のラウンジから漏れ出る笑い声だった。懐かしい声。心臓が高鳴るのを感じながら、美咲の足が止まる。
「そうそう、あの頃はさ」陽野沙織の声が聞こえてきた。「『借手のリース期間』の判断でも大変でしたね。延長オプションがあるかないか、経済的インセンティブの評価とか」
あの明るい声は変わっていない。5年という時の流れを超えて、まったく同じ調子で会話を弾ませている。美咲は思わず壁に身を寄せ、息を潜めた。
「今でも覚えているのか」黒嶺尚吾の声には感心が混じっていた。以前より落ち着いた、深みのある声になっていた。
「もちろんですよ~。『更新がないこと』の事前説明書を探しに、外部倉庫まで走ったんですから」
「思い出した!」黒嶺が沙織に向かって愚痴をこぼす。「あのとき、外部倉庫を恐ろしいほどに散らかしていたよな。その整頓に我々三人が付き合わされて。疲れ切って、打ち上げの気分にもならかったよ」
「ホント、あれは大変だったな」氷倉隆の声が続く。「監査法人との協議が懐かしいよ」
美咲の心が、かすかに震えた。あの計算モデルが、結局役に立ったのか。そして、彼らは自分の突然の退職をどう受け止めたのだろう。美咲は姿を見られたくはなかった。まだ、準備ができていなかった。
「でも、面白いよね~」沙織の声が弾む。「美咲先輩の講演を聞いていて思ったんです。財務諸表とサステナビリティ開示のコネクティビティ。これって、あの時の計算モデルと似ているんじゃないかって」
美咲は驚きに目を見開いた。沙織がそこまで理解していたとは。彼女が自分の講演を聞きに来ていたということも、今初めて知った。一体、どこで聴いていたのだろうか。
「どういうこと?」夜島誠人の声には、かつての詰めの甘さは消え、経理部課長としての重みが感じられた。その声を聞いた瞬間、美咲の胸がきゅっと締め付けられた。
「だって、リースのモデルだって、いろんな要素が絡み合っていたでしょう? 『借手のリース料』から始まって、オプションの判断、経済的インセンティブの評価。全部が繋がっていたじゃないですか」
「なるほど」氷倉の声が深みを帯びる。「サステナビリティ情報も同じだな。気候変動への対応が、将来の収益予測や、設備投資の判断に影響を与える。そこから財務諸表への影響が生まれる」
「ということは」黒嶺尚吾の冷静な声が響く。「彼女は先を見ていたということか」
美咲は思わず目を閉じた。5年前、突然の留学を決意した理由。それは単なる逃避ではなかった。予期せぬ誤解がきっかけで決断を早めたとはいえ、キャリアの方向性を見出した瞬間だった。彼らがそれを理解してくれていることに、美咲は言葉にならない感謝の気持ちを覚えた。
「だったら」夜島誠人の声が、ラウンジの空気を変えた。「俺が霧坂に話を持ちかけてみようか」
その言葉に、美咲の心臓が止まりそうになった。彼は自分を探すつもりなのか。彼が勤務を続けていると聞いてはいたが、もう会うことはないだろうと思っていた。講演の依頼を受けたとき、昔の同僚に会うかもしれないという可能性は頭によぎったが、まさか誠人と再会するとは——。
「相変わらず、君は突っ走るな」氷倉の声には温かみがあった。「でも、それでいい。5年前のプロジェクトだって、君の『俺が全部、更新してやる~』という一言で救われたんだから」
美咲は思わず息を飲んだ。あの日のことを、彼らはそう受け止めていたのか。自分が去った後、誠人が計算モデルの責任を引き継いだのか。そのことに、驚きと感謝の気持ちが込み上げてきた。
“Kiri? Are you okay?”
同僚の声に、美咲は我に返った。「Yes, I’m coming.」
エレベーターに乗り込む前、最後にラウンジの方を振り返る。かつてのメンバーたちは、まだ談笑を続けていた。その穏やかな会話を聞き、美咲は微笑んだ。失ったものもあるが、彼らが確かに存在し、自分のことを覚えていてくれる。それは大きな安心感をもたらした。
それはまるで、5年の時を超えて再び始まろうとする物語の予感のようだった。美咲の胸に、懐かしさと期待が入り混じる。
“You look happy.”
エレベーターの中から覗く同僚の言葉に、美咲は小さく頷いた。
「Because I found my old calculation model is still working. And maybe…」少し間を置いて続けた。「it’s time to create a new one.」
夕闇が迫る窓の外で、街灯が一つ、また一つと灯り始めていた。それは彼女の心の中で、再び動き出そうとする歯車のように見えた。
エレベーターのドアが閉まり、美咲は新しい未来へと向かっていった。そこには、きっと彼らとの再会が、そして新たなモデルの構築が待っているはずだった。