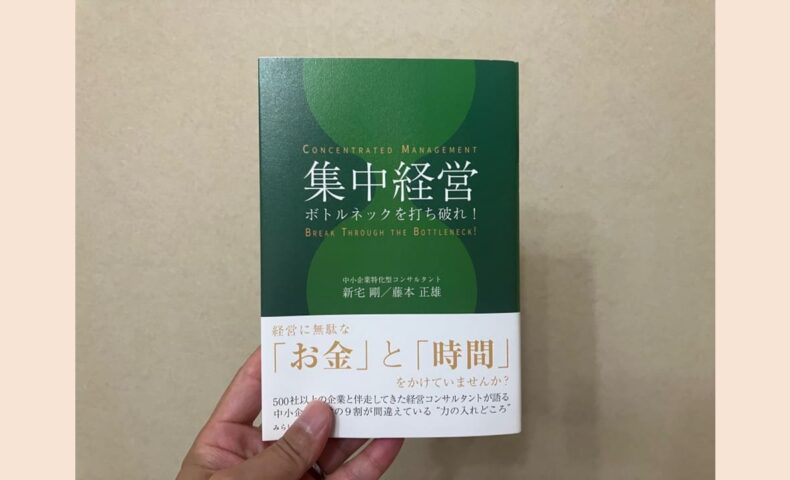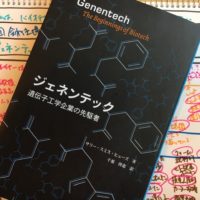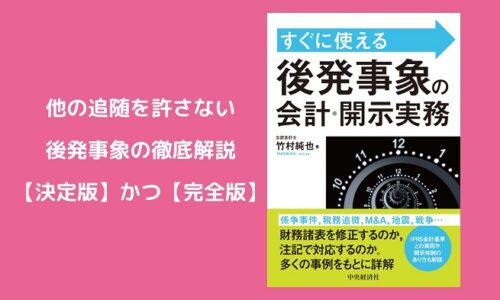経営の現場において、課題が山積するあまり、何から手をつけるべきか分からず停滞してしまう。そんな状況は、決して珍しいものではありませんよね。特に中小企業のように、人手やお金などの経営資源が限られている組織では、「すべてに少しずつ手をつける」という一見バランスの取れた対応が、かえって成果が出にくくなったり、進捗が止まってしったりとする原因になることがあります。
このような構造的な混乱を打破する明確な指針として注目すべき一冊があります。それが、新宅剛氏と藤本正雄氏による共著『集中経営 ボトルネックを打ち破れ!』(みらいパブリッシング)です。本書は中小企業経営者を主な読者に想定して書かれているものの、その対象範囲は非常に広く適用できるため、マネジメントに悩む大企業の管理職から、複雑なプロジェクトを統括するリーダーまで、幅広い層に深い示唆を与える内容となっています。
■経営の「ムダや停滞の原因」を仕組みとして明らかにする
本書の中心にあるのは、「ボトルネック」(仕事の流れを止めている要因)をはっきりと可視化することで、そこに経営の力やリソースを集中させるという考え方です。成果創出を阻む障害として、著者らは「内容の壁」「理解の壁」「感情の壁」「行動の壁」という4つのフェーズを提示します。この分類は成果が生まれる順番でもあるため、いわゆるMECE(漏れなくダブりなく)的な整理となっています。こうして効果的にボトルネックを洗い出しやすくしている点が本書の特徴と言えるでしょう。
従来では、「なぜ従業員が動かないのか」という問いに対して、「やる気がない」「能力不足だ」といった表面的な分析で終わってしまうこともあったでしょう。しかし、本書は違います。情報の伝達不全、認識のズレ、心理的抵抗、そして実行力の不足という、目に見えづらい要因を段階的に整理することで、問題の根本に迫ろうとするのです。
さらに、この4つの壁に対応する形で、改善すべき経営改善領域が5つに整理されています。具体的には、「経営者の軸」「会社の方向づけ」「人材育成・採用」「組織連動・仕組み」「実践と振り返り」です。ボトルネックの洗い出しだけではなく、リソースを配分すべき領域を明確に可視化される構成にもなっています。
この考え方の枠組みは、複雑な経営の現場で、「何をやるか」ではなく「何をやらないか」を決めるための指針として大いに役立ちます。やることを決めるのは簡単ですが、やらないことを決めるのは勇気が要りますからね。
■理論を実装する仕掛け
どんなに良い考え方でも、現場で使えなければ意味がありません。本書では、10の自己診断的な問いや「集中経営実践ワークシート」など、読者自身が自社のボトルネックを洗い出し、かつ解決に向けて具体的に行動できるよう支援するツールが豊富に用意されています。
これらのツールが秀逸なのは、単なるチェックリストではなく、経営の問題を他責ではなく内省の対象として捉える風土を育むことを意図している点です。外部環境や競合他社のせいにするのは簡単ですが、真の変革は常に内側から始まるものなのです。こうした内省的なアプローチが根付くと、現場主導の変革が可能になります。
また、随所に共著者が影響を受けたビジネス書の紹介が挿入されているとともに、巻末にはその一覧も収録されています。これは単に参考書を紹介しているだけではなく、本書を中心にして「集中経営」に関する知識が広がるように工夫されているのです。知識は孤立して存在するものではなく、相互に関連し合って価値を生むものですからね。
■読書会という「秘密兵器」
書籍『集中経営』のもう一つの魅力は、そのフレームが組織内対話の土台として機能し得る点です。ここで私が強く提案したいのは、読書会という実装手段なのです。本書で紹介されたビジネス書を題材とした読書会を社内で開催することで、「4つの壁」のうち、いま自社に最も強く立ちはだかるのは何かをチーム全体で探ることができます。
このプロセスは、単なる読書を超えた「組織の自己認識」を促す営みであるのと同時に、経営者と現場をつなぐ共通言語の構築にもつながるのです。個人の学びと組織の変革を橋渡しする方法として、読書会ほど手軽かつ効果的な手段はそう多くないでしょう。
読書会の効用は、知識の共有だけではありません。異なる部署、異なる階層の人々が同じテキストについて語り合うことで、組織内に眠る多様な視点が浮き彫りになります。マーケティング部門の担当者が見る「理解の壁」と、営業部門の担当者が感じる「行動の壁」は、おそらく全く違うものでしょうからね。
■情報過多時代に必要なのは「選択と集中」の技術
現代の経営者やマネジャーが直面しているのは、情報不足ではなく情報過多の問題です。毎日のように新しい経営手法、マーケティング戦略、組織論が登場するため、「これも重要、あれも必要」という状況に陥りがちです。しかし、経営リソースは有限です。すべてに手を出せば、結果としてどれも中途半端に終わってしまうでしょう。
経営とは、限られた人やお金をどうやって一番効果的に使うかを考える知的な仕事です。そして最も困難なのは、「何に集中すべきか」を見極めることです。書籍『集中経営』はその根本的な問いに真正面から向き合うことで、単なる精神論ではなく、具体的な方法論と実践ツールを提供しているのです。
本書の真の価值は、構造化されたフレーム、内省を促す問い、そして組織対話の起点という三つの要素がうまく組み合わされている点にあります。多くの経営書が理論の紹介で終わってしまうのに対し、この『集中経営』は読者が実際に行動を起こせるよう設計されているのですね。
この本は、ただの理論書ではなく、実際に使える「経営の設計図」になっています。組織が複雑さに呑まれることなく、本質的な課題に集中するための実践的なガイドブックとして、多くの経営者・マネジャーにとって手元に置く価値があるでしょう。読んだだけで終わらせる本ではなく、読んだあとにすぐ動き出せる本です。
P.S.
共著者のおひとりの新宅さんと初めてお会いしたのは、今から15年近く前のこと。当時は、お互いが同じビジネス書を読んでいたことで盛り上がりました。そんな新宅さんらしさが書籍紹介に表れています。