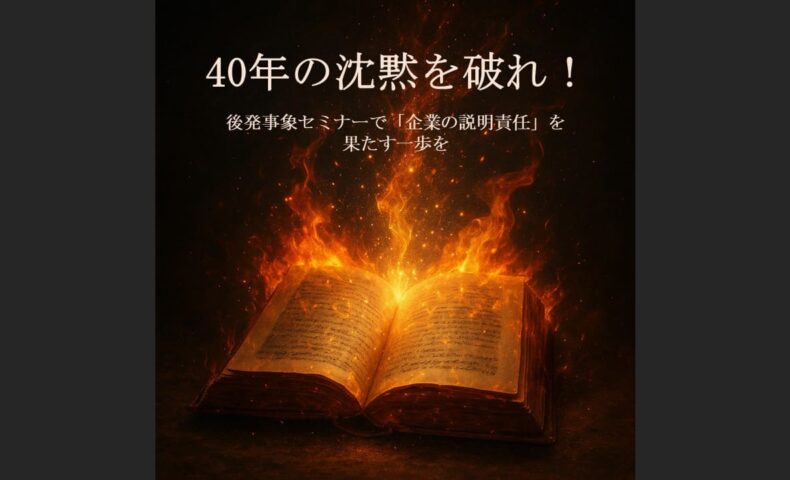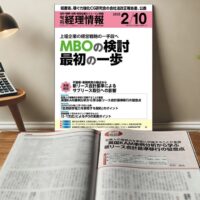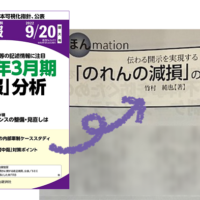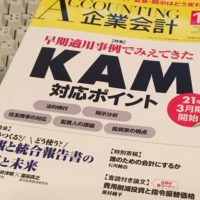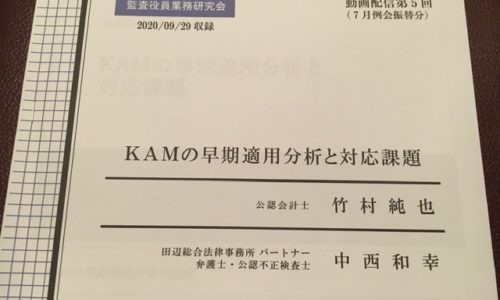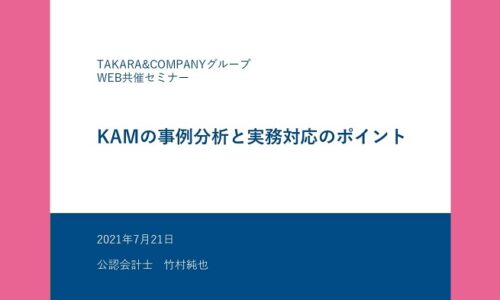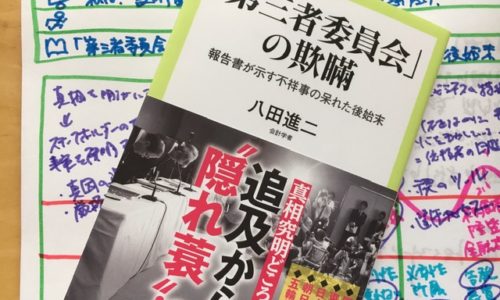会社法決算を締め、会計監査人が監査報告書を提出したその翌日。もし、利益を半分以上吹き飛ばす修正後発事象が生じたとしたら?
「後発事象の取扱いに従って、注記しておけばいいんじゃないか」
確かに、現行の取扱いに従えば、それで問題ありません。しかし、投資家、特に海外の投資家はその注記に果たして納得するでしょうか。
これは単なる技術論ではありません。企業の説明責任を果たすかどうかの分岐点なのです。
■40年の沈黙を破ったはずが…
2025年7月5日、ASBJはついに「後発事象に関する会計基準(案)」等を公表しました。その内容は次の3つのポイントに集約されます。
- 評価終了日の設定:「財務諸表の公表の承認日」を基準とする
- 評価終了日の注記:財務諸表にその日付と承認機関・者を記載する
- 特定期間の例外措置:修正後発事象の特例を現行通り踏襲
一見すると整った提案に映るかもしれません。しかし、その実態は「現行実務の追認」。例外措置はそのまま温存され、制度的矛盾を解決するどころか固定化するリスクをはらんでいます。
この状況は、まるで砂の上に家を建てるようなもの。会計基準の上では成立していても、信頼は揺らぐ。
なぜなら、会社法では「確認日」、金商法では「公表承認日」と評価終了日が二重化し、さらに修正後発事象は「注記止まり」。これでは「数値を守るか、信頼を守るか」という根源的な矛盾が残り続けるのです
■セミナーで解き明かすこと
2025年10月23日のセミナー「後発事象の“現行実務”と“基準案”を一挙解説 ~現行実務の構造と公開草案の懸念点を徹底分析~」では、こうした矛盾を正面から解き明かします。
- 現行実務の盲点と二重構造の正体
- 公開草案の3つのポイントと残されたリスク
- 実務者が“今”から備えるべき具体的な対応策
単なる制度解説ではなく、歴史・制度・実務を一つの物語として結びつけることで、行動に直結する知見を提供します。後発事象を基準として学ぶのではなく、実務として理解し、現場でどう生かすかを掴む時間です。
■今こそ動くべき理由
この問題は、経理担当者だけの話ではありません。監査役、法務、IR、投資家対応など、企業に関わるすべての人に直結します。
基準が動き出すとき、準備していた企業とそうでない企業の差は歴然。説明責任を果たせるかどうかで、信頼という見えない資産の価値が決まるのです。
だからこそ、いま。このタイミングで、あなたにお伝えします。
あなたが動けば、未来を変える最初の一歩になるのです。
P.S.
会場参加なら、セミナー終了後にも個別の意見交換が可能です。ただし、会場スペースの関係上、お席には限りがあるため、お早めに確保されることをお勧めします。