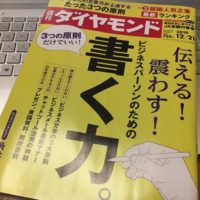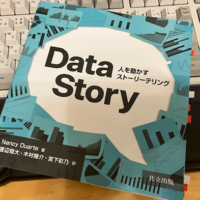やっぱり本が好き。なんてったって、それまで知らなかった世界が読書を通じて知ることができるのがいい。それがビジネス書でも、小説でも。
また、好きなのは、本だけではありません。その本をどう読むかという「読書術」も好きなんです。好きな本に、どんなアプローチができるのかを知ることで、その数だけ楽しみ方も増えるから。
振り返ると、その原体験は大学受験にあるのかも。当時は、国語が大の苦手。どうやって文章を読み解くのか、そのアプローチの仕方がわからなかったのです。その原体験までは、国語や現代文の先生は、経験で読み解くアプローチしか教えません。
しかし、それでは再現性がない。ということは、大学受験までに現代文で合格点を取るのが厳しいことを意味します。加えて、ボクが育ったのは、石川県の金沢。当時、受験予備校で名を馳せていた河合塾も代々木ゼミナールも、金沢には教室を設置していませんでした。だから、本屋さんにある参考書だけが、学校教育以外の唯一のチャネルだったのです。
何とかしなければと思い、参考書をいろいろと調べました。あっ、この頃から調べまくる習性があったのですね。確かに、気に入ったものがあると、とにかく集めまくっていたっけ。
そこで、出会った参考書が、『田村の現代文講義』シリーズ。代々木ゼミナールの講師である田村秀行サンが書かれたもの。論文の読み解き方はもちろん、小説の味わい方も、日本語の読み解き方はすべて、この参考書で学びました。
目から鱗が落ちるって、まさにこのこと。百万枚もポロポロポロポロ落ちた感じ。このアプローチを学んでからは、現代文への苦手意識はなくなりました。こんな体験があるものだから、心のどこかで、現状よりも良いアプローチがあるものだと思うようになったのかもしれません。
時間を現在に戻すと、今の楽しみといえば、読書。だからか、読書へのアプローチにも興味津々。いろんな読書術を調べ、また、試しています。今のボクの読書術のベースになっているのは、「フォトリーディング」。これは、アメリカでポール R.シーリィ氏が開発したもの。それを神田昌典サンが日本に持ち込みました。
フォトリーディングのやり方は、『あなたもいままでの10倍速く本が読める』(フォレスト出版)という本で詳しく説明されています。ただ、ボクはどうしても気になったため、フォトリーディングの講座を受講しました。速読が身につくだけではなく、能力の限界も外してくれたのが良かった。
この講座を受けてから、意識的にフォトリーディングを使う機会を使おうと、ひたすら乱読。ひと月に新しく読む本は20冊以上というペースで読書してきました。このペースを4年近く続けていたので、この期間だけでも1,000冊近くは読んだ計算。当時、勝間和代サンが、「自分をグーグル化する」と表現していたことを体現していました。
本に書いてある情報を速く収集できると、アウトプットも多くなります。アイデア本で有名すぎる、ジェームス W.ヤング氏の『アイデアのつくり方』(CCCメディアハウス)では、アイデアとは既存の要素の新しい組み合わせだと説明されています。つまり、インプットの量が多いほどに、アイデアが生まれやすくなるため、アウトプットも必然と増えていくのです。
10のインプットと1,000のインプットとでは、どちらがアウトプットしやすいかは自明。だからこそ、ボクも本業の傍ら、ほぼ毎年一冊のペースで本を出し続けられたのです。本やセミナーなどで「教える」「伝える」ことをしている人なら、速読術は身につけていて損はない。コンテンツを深めるなら、まずは、インプット力を高めないとね。
このフォトリーディングをさらに活用しやすい形で提供していると感じているのが、渡邊康弘サンが開発した「レゾナンスリーティング」。この読書術は、『1冊20分、読まずに「わかる!」すごい読書術』(サンマーク出版)で説明されています。
今のボクの読書術は、もっぱらレゾナンスリーティング。さらりと読み流す本でなければ、このアプローチをひたすら使っています。著者と対等になれる本の読み方が、お気に入り。本の内容を自分事にできるばかりか、行動計画にもつなげやすい。つまりは、インプットしたことをアウトプットにつなげられやすい、ってこと。
そんな読書術は突き詰めていくと、すごい方向にも行きます。それは、「読まない」というもの。別にふざけているワケではありません。パリ第八大学教授で精神分析家のピエール・バイヤール氏は、『読んでいない本について堂々と語る方法』(筑摩書房)という本を書いているのです。読めば、真っ当な内容だとわかるハズ。
このアプローチを知っていれば、経験で読み解くことしか言わない国語や現代文の先生に振り回されずに済んだのに。そんな世界も知ることができる本って、すごい。やっぱり本が好き。