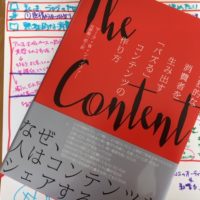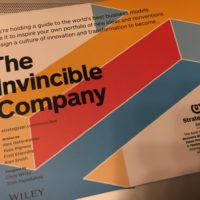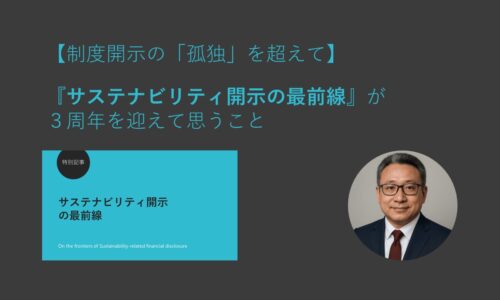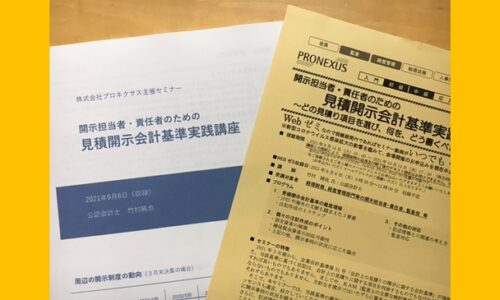日本で、選挙はどれくらいの頻度で行われているか、ご存知ですか。
半年に1回程度? 3ヶ月に1回程度? それとも、1ヶ月に1回程度?
昔、何かの集まりで、選挙に関するビジネスを手掛けている人に出会ったことがあります。選挙が開かれることになるとその地に駆けつけて、のぼりやチラシ、垂れ幕などの選挙用品を手配する仕事。
確かに、選挙は、急遽、開催されると決定される場合もあります。また、定期的に開催される選挙であっても、間際になって立候補することになる人もいます。すると、立候補は事前に準備できないことも珍しくない。そんなときに、こうして事務手続をサポートしてくれる仕事に需要が生じます。
ただ、いくら需要があっても頻度が少なければ、ビジネスとして成立しない。例えば選挙が数ヶ月に1回程度の開催じゃ、とても継続していけないのは明らか。それを尋ねたときに、その方から投げかけられたのが、最初の質問。
そのときに教えてもらったのが、なんと、週に1度の頻度。参議院や衆議院といった全国区の選挙だけではなく市町村の選挙まで含めると、毎週、全国のどこかで選挙が開催されている計算になるそうです。なるほど、そこまでの頻度があれば、ビジネスは成り立ちます。
選挙で、そうした裏方のサポートには、とても関心してしまいます。ユーザーの悩みを解決しているのですからね。ビジネスの基本は、誰かのペインを取り除く・減らすか、あるいは、ゲインを付け加える・増やすかのいずれか。その大原則に則っています。
しかし、選挙の表に立っている人、すなわち、立候補者の主張は、マーケティングやコピーライティングの観点からは、なかなかいただけない。最近、とある業界で選挙があったものだから、ついつい、そんな視点で見てしまいます。
マーケティングの世界では、消費者が商品を認知してから買うまでの過程を示した「AIDAの法則」が有名です。これは、Attention(認知)、Interest(興味)、Desire(欲求)、Action(行動)の頭文字。
まずは、Aの認知。票を持っている人を振り向かせることに失敗しているものが多い。ここでは、有権者の関心を引くような声がけが必要。マーケティングの観点からいえば、有権者にとってどんな問題が生じているのかを説くべき。
次に、Iの興味。有権者に関心を抱かせるような話を提供していないのも多い。問題を提示したら、何が原因で問題が生じているのかを説明していくのが王道。
その次は、Dの欲求。「~の実現」や「~の社会を」と綺麗なお題目を掲げてはいるものの、それをどうやって達成するのかまでは言及していないものも多い。ここでは、立候補者の提示する政策がぜひ叶ってほしいと思わせる段階。問題の原因を取り除いたり、軽減したりする政策を具体的に述べるのです。ビジネスの基本と同じ。
最後に、Aの行動。これまでの認知、興味、欲求の段階を経た後に、投票を呼びかけるのが鉄則。ひたすら「清き一票を!」「どうか、男にしてください」と頭を下げるばかりじゃ、「知らんがな」で終わってしまいます。
ちなみに、プロフィールの書き方もなっていない人も散見されます。そこに書いた経験が、問題解決にどう役立つのかがわからないとダメ。何も関連がない事項を書き連ねても、何の効果もない。自慢と捉えられて、むしろマイナスの効果すら生じかねない。
マーケティングでは購買を、一方、選挙では投票を呼びかけます。このように行動を呼びかけるという点では、両者はまったく同じ。ならば、ある世界で効果が得られている手法を別の世界で活用しない手はありません。だってほら、顧客や有権者があなたの提案に振り向かなきゃ、日本の損失になってしまうじゃありませんか。