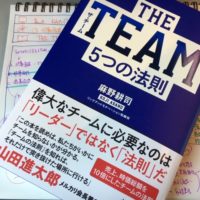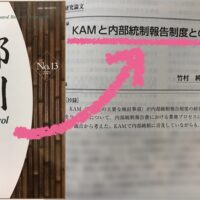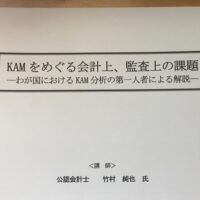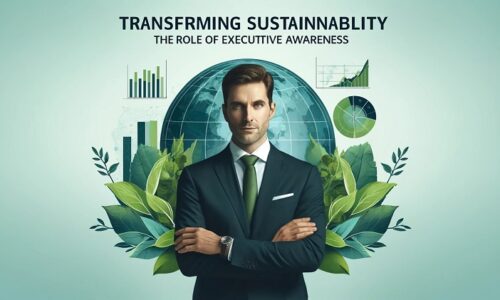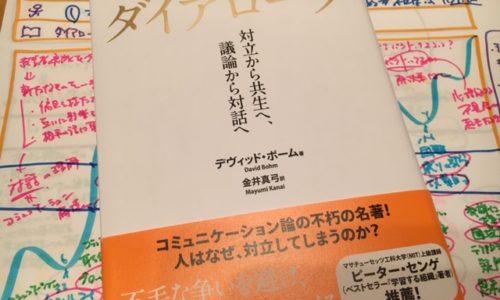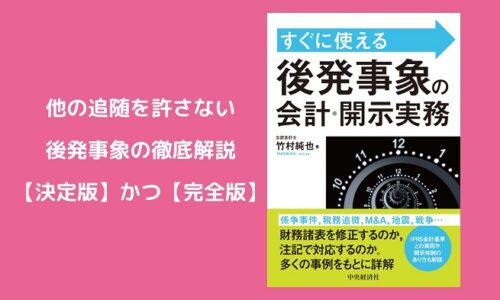2019年3月期の決算の目玉は、税効果会計の注記。BSで非流動とする取扱いもありますが、すでに四半期決算から行っているため、その改正は特に目新しくはない。一方、注記は、早期適用をしていなければ、この期末決算から新たに求められる事項。
このニューメニューのうち実務で悩ましいのが、「評価性引当額の内訳に関する情報」の注記の仕方。特に悩ましいのは、繰延税金資産から控除された額(評価性引当額)に重要な変動が生じている場合の、その変動の主な内容。
ただ、企業会計基準第28号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」には、記載例が示されていないのです。ASBJサンの審議の過程では、具体的な事例を提示したうえで検討が行われていました。
しかし、評価性引当額の変動の内容は企業の置かれている状況により様々。また、具体的な開示例を示すとかえって実態に合った注記がなされない。よって、記載例が例示されないこととなったのです。
とはいいながら、この規定に該当するなら、評価性引当額の重要な変動について主な内容を記載しなければならない。これについて、実は、1年ほど前のセミナーで解説しています。それは、2018年3月29日にプロネクサスさんで開催した「改正税効果会計の概要と実務上の留意点」。基準に書いてない話も盛り込んでの120分。
受講された会社さんは検討のネタを手に入れたため、十分に対応できるでしょう。それに対して、受講できなかった会社さんは対応に苦慮しているんじゃないでしょうか。
当時よりも働き方改革が進み、また、残業時間の上限規制が2019年4月から適用。加えて、ゴールデンウィークは史上初の10連休。今年の決算は、経理部門をはじめとした財務報告に関わる人たちにとって十分な検討時間を確保しにくい状況にあるからです。
そうした人たちのお役に立てるならと思い、昨年に実施したセミナーの一部をシェアすることにしました。セミナーでお伝えしたのは、注記が求められた趣旨。実は、財務諸表利用者にとって、従来の注記では将来予測がしにくかったという背景があります。
評価性引当額の合計額に重要な変動が生じているときには、税負担率に重要な影響が生じていることが多い。しかし、その変動の内容を理解できないがゆえに、税負担率に影響が生じている原因を分析できない。その結果、税負担率の実績と予測が大きく乖離することが少なくなかった。
財務諸表利用者は、評価性引当額の変動の内容を理解でき、また、税負担率に影響が生じている原因を分析できるようにもしたい。そこで、定性的な情報として、その変動の主な内容について注記することが求められたのです。
このように、評価性引当額の変動内容の記載が追加された趣旨は、主として税負担率の分析に資することにあります。こうした分析に役立ちうるために期待される定性情報を考えたときに、例えば、次のような内容が考えられます。
- 将来の合理的な見積可能期間における課税所得の合計では解消できない税務上の欠損金が新規に、あるいは、追加で生じた。
- 税務上の繰越欠損金が課税所得に充当された。
- 税務上の繰越欠損金に繰越期限切れが生じた。
- 将来の合理的な見積可能期間における課税所得の合計では解消できない将来減算一時差異が生じた。
- 将来の合理的な見積可能期間における一時差異等加減算前課税所得の見積額が減少した。
つまり、「評価性引当額の増減」が一過性の原因で生じたものかどうかを判別できること、それがポイントと考えられるのです。
もちろん、早期適用の事例を分析することでも注記の内容が理解できることもあるでしょう。この件に限らず、会計士でも企業の方でも、やたらと事例を知りたがる人がいます。
しかし、それでは「何が書いてあったか」しかわからない。また、事例が間違っていることもあります。さらに、間違っていなくても、その開示事例の会社とは置かれた環境とは異なるなら、それとは違う開示の仕方にすべき。
事例をマネするのではなく「何を書くべきか」を探るなら、制度趣旨を踏まえるのが一番良い。そんな想いから、1年前の、まだ早期適用の開示事例が入手できない時点でありながらも、注記する内容を例示したのです。
こんな感じでボクのセミナーでは、知恵を絞った内容を紹介しています。本も同じ。ブロクもたまにお話ししています。あなたはどれをフォローしますか?