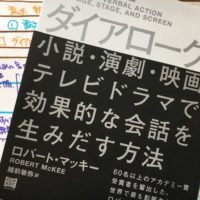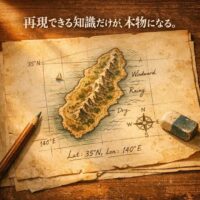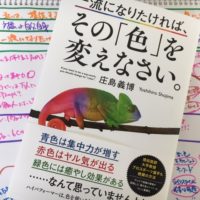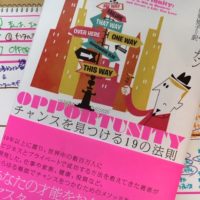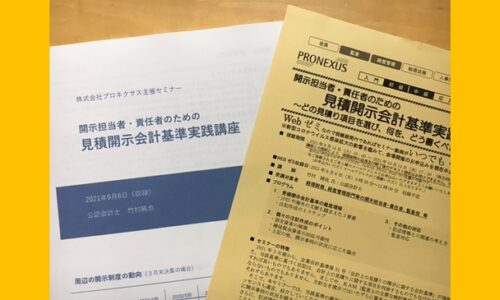今日は、大学のゼミのOB・OG会に出かけてきました。ゼミの先生が定年を迎えるということで、1期生からまだ現役の37期生までが集まった会。ボクは9期生のため、4分の1くらい上の世代でした。
最寄り駅から会場となった大学へと向かう途中、商店街の通りではハロウィンの仮装イベントが行われていました。近所の人たちや商店街の人たちが仮装して歩いています。
ボクがこの辺りに住んでいたのは30年近く前のため、ハロウィン自体がまったく浸透していない頃。だから、そんな催しがこの地で開催されていることに驚きました。まったく、随分と変化したものです。
仮装して歩いている親子は、仮面ライダーのショッカーのような、黒の上下に白地で骨がプリントされているものを着ていたり、カップルは顔から血を流しているメイクでいたりと、日常とは違う装いで楽しんでいます。これも、日常からの変化ですね。
そんな道を歩きながら、ボクらもゼミの中で変化していたと思い出しました。それは、論文の書き方もあれば、ゼミでの発表の仕方もあります。その他にも、参考文献の調べ方などもありました。
こうした指導を通じて、一研究者としての姿勢や社会人としての姿勢を身につけていったのです。そう、変化したのです。変容と言っても良いかも。
最も印象に残っているのは、当時に、ゼミでの先生が話した言葉。今でも忘れずに大事にしています。それは、ゼミの終わりの卒業間近の頃。先生はゼミ生に向かって、こう話したのです。
「何かを話すときには、歴史と理論と実務を調べなさい」、と。
何事にも現状に至った過程があるから、それを踏まえて考えないといけないこと。また、何かを考えるにしても、あるべき理論を押さえること。さらに、理論とは別に、実際の現場では何が行われているかも理解すること。これらについて、「歴史と理論と実務」と表現されたのです。
これは、ボクの執筆スタイルにも反映されています。例えば、『後発事象の実務』(中央経済社)を書いたときには、まさにこれ。まず、後発事象が企業会計原則に規定された当時の資料までさかのぼって、位置づけを調べました。これが歴史。
次に、後発事象に関する論文を片っ端から集めたうえで、展開されている理屈を整理しました。幸い、後発事象を扱った論文はそう多くはなかったため、収集の手間は少なくて済みました。もちろん、海外的な会計基準の取扱いもチェック。これが、理論。
さらに、執筆していた当時の過去3年間における上場企業で開示後発事象とした内容を調査しました。開示の頻度が高い事象を抽出したうえで、そこから過去7年くらいさかのぼって該当する事例の記載をすべて検討しました。これが、実務。
ゼミの先生の言葉がなければ、あの本はこうした内容にはなっていなかったでしょう。あのときの一言が、ボクの執筆スタイルに大きな影響を与えています。もちろん、後発事象以外の本でもそう。徹底的に歴史と理論と実務を調べる姿勢は同じ。
こうしてゼミを通して変化したことを噛み締めながら、会場に向かいました。会場に着くと、昔のままの笑顔で先生が立っている。多少、老けた近い年代の人たちも集まっている。気分は一気にタイムスリップ。まるで、トリックをかけられたように。そんなハロウィンの一日でした。