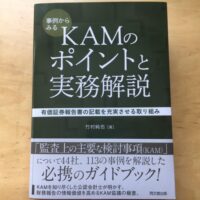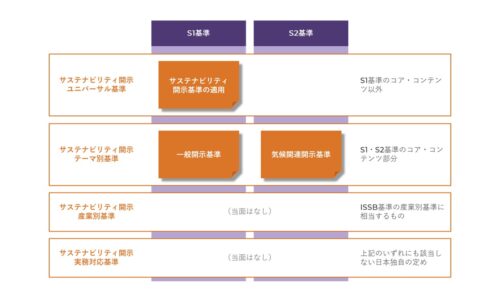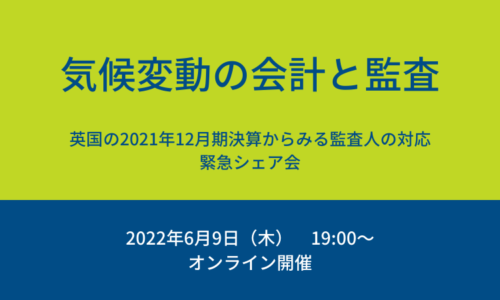昨日のブログ「有報の作成者に、1つ、お願いがあるのですが。」では、記述情報に関するセミナー企画について、あなたのご意見を伺っています。22時37分に記事をアップしたにもかかわらず、その夜にアンケートを回答してくださっています。
アンケートにご回答いただいた方々、また、ブログ記事を拡散してくださった方々に感謝申し上げます。本当に嬉しいです。
2019年11月11日(月)12時までの回答状況によって、セミナーを開催するかどうかを決定しますので、奮って、ご回答ください。
せっかくなので、これまでボクがブログで記述情報に関連してお話ししてきた記事をまとめてみました。記事のタイトルと内容を記載していますので、ピンと来たものをクリックして、セミナー企画の検討にご活用ください。
===ここから===
2019.03.20
開示事例の分析はボクにお任せあれ
今回は金融庁サンが率先してリリースしたものの、本来的には民間側でこうした取り組みをやるべき。今後はKAMの事例も出てくるため、企業側の開示、KAMの記載ともに、良い事例を選別したうえでシェアする組織が必要なんじゃないでしょうか。
2019.03.21
投資家との対話を促すダイアログ・ディスクロージャー
ボクがサポートしたいのは、十分に理解してもらうための開示の仕方。不要なコミュニケーションに要する時間を削除し、かつ、より発展的な対話を促すための開示を行っていくのです。名づけて「ダイアログ・ディスクロージャー」。
2019.03.25
「重要な会計上の見積り」開示はこう対応する
「重要な会計上の見積り」の文脈で感応度分析が用いられているのです。その理由は、財務諸表の利用者が自身で財務数値を自由に組み替えられるようにするために提供している情報だとボクは考えています。
2019.05.3
有報の記述情報を経営者視点で書く方法
自ら書くだけではなく、その内容を調整し、また、加筆修正していく過程を通じて、全社のみならず投資家までも巻き込んでいるのです。ここまでCEOが関与している企業開示はお見事。
2019.05.11
『流れとかたち』でコンストラクタル法則を学ぶ
組織の構造は時間軸の中で変化していくため、その時々によって、最適な流れが変わるから。だから、1つの型にはめるのではなく、現状の流れをみたうえでデザインしていく必要があるのです。
2019.05.20
ブレイクダンサーがふいっと見る有価証券報告書
会計処理には詳しいものの、その結果を経営とうまく結び付けられない経理部。一方で、経営には長けているものの、会計処理の結果とうまく結び付けられない経営者。これらが繋がることで、利用者が求める財務報告にシフトしていく。
2019.05.27
有報で感応度分析を記載している企業を調べたら
上場企業が約3,600社とすると、「感応度分析」という用語を記載しているのは、5%程度。S字カーブの理論でいえば、市場普及率が10%を超えると成長期になるため、まだまだ導入期。
2019.07.11
有報の役員報酬の開示はストーリーを語れ
有価証券報告書は、その利用者にとって利用価値が少なくなっていると指摘されています。経営者は、読み応えのない資料を生産していることになる。そんなことにコストを費やしているなんて、もったいなくないですか。
2019.07.23
コンテンツ化に必要な、文字の「見える化」
思考のままでは、頭の中を駆け巡ったあと、どこに行ったのかがわからない。文字にすることで、紙媒体ならメモやノート、付箋紙などに、また、電子媒体ならメールや文書ファイル、クラウドなどに記録が残っている。
2019.08.4
社長、その財務報告では埋没します
有価証券報告書には記述情報を頑張ってたくさん記載しているでしょう。しかし、その記述がどこかで見たような文章で埋め尽くされているなら、他社との違いが生み出されません。つまり、認知されないのです。
2019.09.19
会計基準は「考えるな、感じろ」
根本的な原因は、会計処理することにフォーカスしてことにあるとボクは見ています。そうではなく、財務報告に意識を向けるべき。どう処理するかではなく、どう説明するか。有報の記述情報の拡充の動きも、まさにこれ。
2019.10.23
記述情報の早期適用は酷すぎる
実際、これまで重要な会計上の見積りを記述している会社でも、その記載の深さには濃淡がありました。嘘、っというほどに浅い会社もあれば、見事と褒め称えたいほどに深い会社もあります。
2019.10.30
ASBJに提案「基準開発の予見可能性の高め方」
文書での公表はやめて、ホームページで逐次、発表してはいかがでしょうか。次回のASBJで公表議決にかけましょうと審議された時点をもってアナウンスをするのです。これなら、基準開発の予見可能性を今以上に高められます。
===ここまで===
以上、13記事です。記述情報に関する最初の投稿が、2019年3月。7ヶ月強の期間に13記事のため、半月に一回くらいの頻度で記述情報に関連した話をしてきたことになります。
もちろん、記述情報を直接取り扱ったものもあれば、間接的に触れただけのものもあります。いずれにせよ、ボクの関心が記述情報にあったことには間違いありません。
そこまでに情熱のあるテーマで、ぜひとも、セミナーを開催したい。あとは、あなたのご意見次第。アンケートは数分で終わります。
40名を超える意見で判断しますので、アンケートへのご回答をお待ちしております。▼クリックして、アンケートに答える。(終了しました)