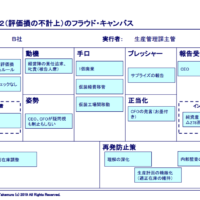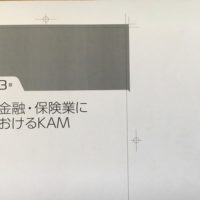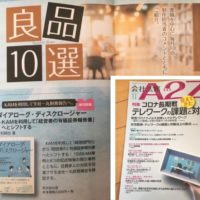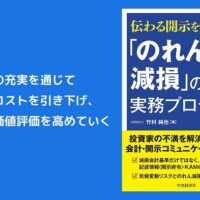昨日の2020年3月1日に投稿したブログ記事「新型コロナウイルスが決算に与える影響」では、あえて2020年3月期の企業については言及していません。2月決算までの企業を想定して後発事象の話をしました。
というのも、新型コロナウイルスのビジネスへの影響が3月から顕在化していることを踏まえると、すでに会計期間の中で関連する会計事象が生じているから。つまり、自ずと決算の中に、その一部が織り込まれているからです。
会計事象が期末日までに生じているなら、何かしらの仕訳を起こさざるを得ません。中には会計上の見積りに関連してくる項目もあるでしょう。将来業績がポイントとなる減損会計や税効果会計、損失を取り込む引当金、債権に対する貸倒見積高などでは、前提や判断に迷う局面もあるかもしれません。
しかし、それと同じくらい、あるいは、それ以上に対応に迫られる論点が考えられます。それは、有価証券報告書における記述情報。「経理の状況」よりも前に文章で記載する箇所。2020年3月期以降から、この記載の充実が求められているため。
今回の新型コロナウイルス感染への対応によって、経営環境が大きく変化した企業もあるでしょう。すると、対処すべき課題も当然に変化し、また、事業等のリスクも項目や優先順位も変わってきます。
加えて、MD&A(経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析)にも影響が及びます。場合によっては、対策部署が設置されるなどしてコーポレート・ガバナンスにも記述を加える状況も考えられます。
このように、何かしらのインパクトが有報の記述情報に及びかねない。コロナウイルスに関連した潜在的なリスクや顕在化したリスクなどについて言及せざるを得ないことが想定されるのです。次の3点について、もう少し具体的にみていきましょう。
(1)経営方針、経営環境及び対処すべき課題等
このブログでも散々、お話ししてきたとおり、新型コロナウイルスに起因してビジネスモデルへの影響があります。チャネルへの影響もあれば、キーパートナーの見直しもあります。こうした経営環境に対して経営者がどのような認識をもっているかを説明することも求められています。
もちろん、これから説明する事業等のリスクやMD&Aと関連付けた内容であることは当然です。経営環境に何も言及されていない中で、その2つの説明に突然、新型コロナウイルスが登場するのは記述として整合していません。
(2)事業等のリスク
ここでは、企業固有の事情に応じたより実効的なリスク情報の開示が求められています。リスクが顕在化する可能性の程度や時期、リスクが顕在化した場合に経営成績等の状況に与える影響の内容、リスクへの対応策を記載するなど、具体的に記載しなければなりません。
また、記載に当たっては、経営者視点からみたリスクの重要度の順とすることも期待されています。新しく生じたリスクだからと言って最後に追加すれば良いのではなく、何番目に重要なリスクなのかが有価証券報告書の利用者にわかるように記載順にも気を払えるとベスト。
最悪なのは、他の箇所で「経営環境が激変」と記載しながら、「事業等のリスク」の記述が何も変わっていないこと。そんなに経営環境が激変したのなら、潜在化しているリスクや顕在化したリスクは当然に変わっているはず。にもかかわらず、前年踏襲の記述では筋が通らない。この辺り、新型コロナウイルスがひとつの試金石となりそうです。
(3)経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(MD&A)
中でも、「重要な会計上の見積り・仮定の開示」がポイントになってくるでしょう。このブログの冒頭でも、2020年3月期以降の企業では、新型コロナウイルスへの対応が会計上の見積りに関連する可能性があると指摘しました。
この騒動が収束する時期にもよりますが、影響の及ぶ範囲や金額の見積りが難しい状況に立たされていることも十分に想定されます。ライブや公演などを主たる事業としている企業では、公演の中止や延期という形ですでに業績に影響が及んでいます。
これを会計上の見積りに反映するにあたって、業績に予期せぬインパクトを与える可能性も否定できません。記述情報の導入の趣旨を踏まえると、経営陣が関与した中で、重要な会計上の見積り・仮定の開示を充実させることが期待されます。
このように3点だけを取り上げても、新型コロナウイルスへの対応が記述情報にインパクトがあることが理解できるでしょう。
だからと言って、キーワードとして埋め込めば良いってもんじゃない。大きな影響がない、何も考えていない場合に、まるで流行を追いかけるようにコロナウイルスと記載しても何の意味もない。自社にとって固有のリスクであるからこそ、記述情報に反映されるべきものなのです。
したがって、取締役会をはじめとして然るべき会議体で具体的に議論されていなければ、記述情報でコロナウイルス関連に言及しているのは、おかしい。また、議論していることの証跡を残すのであれば、議事録といった形で何をどう議論したのかを残しておくことも必要です。
さらにいえば、記述情報の作成にあたっては、ライティングのための素材をいかに揃えておくかが鍵。記述情報のことまで考えて議事録などで議論の過程や結果の記録を残しておけるのがベスト。
財務報告に関連している方々は、決算や開示を見据えながら、冷静に対処していきましょう。特にニューメニューの記述情報は要注意です。