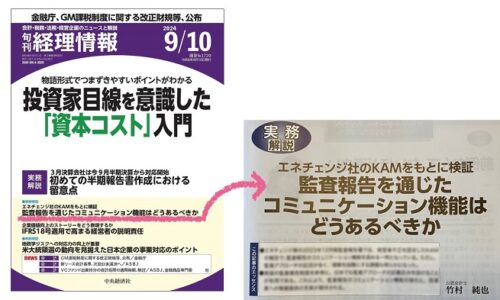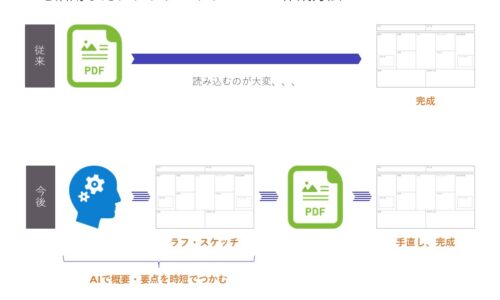SSBJ基準の最終化に向けた審議が、良くない方向に進んでいます。
特別記事「統一か、適応か。SSBJが直面する基準策定の葛藤とその解決策」で解説したとおり、公開草案に対するコメントは大きく2つの見解に分かれています。ひとつは、国際基準であるISSB基準に限りなく近づけるべきだとする「統一基準派」、もうひとつは、日本国内の実情に即した基準が必要だとする「適応基準派」です。
こうした相反する意見の板挟みとなる中、SSBJは、国際基準とのバランスを取る「二重アプローチ」を採用しようとしています。これは、特別記事「実務対応基準の必要性浮上:混乱回避のためのSSBJの対応」で述べたように、基準本文はできる限りISSB基準と一致させつつ、基準外で実務的なガイダンスを提供する方針です。ここでいうガイダンスとは、具体的には事務局が提供する「解説記事」を指します。これは規範性を持たない資料のため、SSBJの正式な審議を経ずに発行されます。
当初、この方針の柔軟性を評価していたところ、審議が進むにつれて解説記事による対応が増えすぎているため、質と量の両面から基準の不十分さを補うものとして機能してしまう懸念が出てきました。つまり、「準基準」化して独り歩きする可能性です。
そこで今回の特別記事では、第42回のSSBJ会合での審議状況と、解説記事の提供が抱える問題点について詳しく解説します。具体的には、次のような内容です。
■温対法と最新の地球温暖化係数に求められる整合性
■最新の地球温暖化係数への再計算の要否
■再公開草案が決定!GHG排出量報告で企業が直面する期間調整
■地球温暖化係数の再計算を不要とする根拠が崩れる懸念
■増える解説記事、減る規範性:SSBJ基準が抱える透明性と信頼性の課題
■「準基準」として独り歩きする解説記事が企業に与える影響
■今回の3つの重要ポイント
この記事を読むことで、地球温暖化係数の再計算が不要とされた背景が学べます。また、報告期間調整の必要性と矛盾点を理解することができます。さらに、SSBJ基準とISSB基準のバランスを取る「二重アプローチ」に関する知見を得ることで、国際・国内での基準を意識した対応がしやすくなります。
ぜひ、この機会に購読し、限定コンテンツを通じてより深い知識を得てください。あなたのビジネスに直結する情報を常に先取りしましょう。