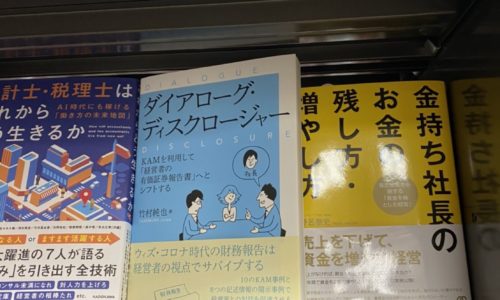サステナビリティ基準審議会(SSBJ)が最終化に向けて審議を進めてきたサステナビリティ開示基準は、ついに公表議決を迎える段階に入りました。2025年2月6日に開催されたSSBJ会議において基準の見直し作業がほぼ完了したため、次回の会議で正式な公表議決が行われる予定です。
この会議では、2024年3月の公開草案から変更する箇所が審議されました。これは、ISSBによるIFRS S2の修正動向を踏まえた最後の議論です。どのような修正動向かについては、特別記事「ISSB基準の修正議論、グローバルの変化を先取りせよ」や「2025年1月ISSB会議が注目するGICS使用要件」で紹介してきたとおりです。
しかし、SSBJは、2025年3月に確定基準を公表することを目指していることから、スケジュールの制約からISSBによるIFRS S2の最終的な修正を待つことができない状況です。このため、IFRS S2の修正動向を考慮しつつ、独自の判断で基準の見直しを進める必要がありました。この過程で、2024年3月の公開草案からの変更が生じました。
そこで今回の特別記事では、GICSコードの採用提案と、それに対する国内外からのコメント対応について詳しく解説します。その内容は次のとおりです。
■12月決算企業にも配慮、SSBJが描く迅速な基準改訂ロードマップ
■SSBJが当初、GICSコード採用を提案した理由
■GICSコード義務化に企業が反発!その背景に潜むコストと誤解
■ISSBの新提案、GICS義務化の再考で企業に広がる選択肢
■SSBJが選んだのは「開示免除」-4つの案から導かれた決断の理由
■ISSB基準改訂なしならどうする?SSBJが直面する2つの選択肢
■日本企業はどう動く?国際基準と実務負担のはざまで求められる対応策
■この記事の3つの重要ポイント
この記事を読むことで、GICSコード義務化を巡るISSBとSSBJの最新動向を把握できます。また、SSBJが経過措置を採用した具体的な理由や議論の経緯を理解できるため、企業の今後の対応方針を検討するための重要な視点が得られます。さらに、SSBJがどのように国際基準と日本の実務環境を両立させる戦略を立てているかを明確に把握できます。
この機会にぜひ購読し、限定コンテンツを通じて、より深い知識を身につけてください。あなたのビジネスの未来に直結する情報を常に先取りしましょう。