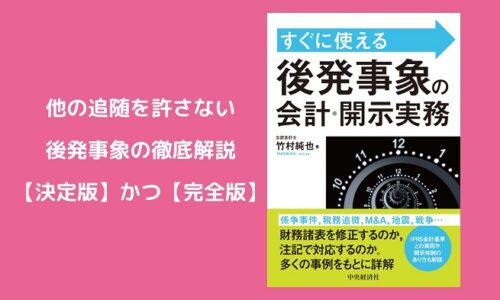気候関連のサステナビリティ開示において、温室効果ガス(GHG)排出量の測定と報告は、企業が直面する主要な実務課題の一つです。特にスコープ3──すなわち、バリューチェーン全体における間接的な排出──に関しては、多くの企業が対応に苦慮しているのが現状です。
こうした状況を踏まえ、IFRS財団は、GHG排出量の測定実務をテーマとしたウェビナーを開催しました。本ウェビナーでは、ISSB(国際サステナビリティ基準審議会)の枠組みに加え、GHGプロトコルを含む国際的なガイドラインに基づく実務のポイントが、外部の専門家の知見を交えながら具体的に解説されました。企業にとっては、測定精度の向上やリソースの最適化につながる貴重な情報が得られる内容となっています。
そこで今回の特別記事では、このウェビナーの要点を整理するとともに、実務に即した補足解説を加えながら、企業が直面する課題とその解決策を明らかにします。その内容は次のとおりです。
■IFRS財団のウェビナー:GHGプロトコルの活用
■企業にとってのスコープ3排出量の重要性
■スコープ3カテゴリーの重要性評価基準
■GHGプロトコルの活用における課題と
■課題を克服するための戦略的アプローチ
■IFRS S2とGHGプロトコルの連携による精度向上
■スコープ3排出量の報告プロセスを改善する実践的アプローチ
■今回の3つの重要ポイント
この記事を読むことで、企業はスコープ3の15カテゴリーのうち、自社にとって重要な排出源を的確に特定するとともに、報告対象の優先順位を明確にする手法を理解できます。これにより、限られたリソースを効率的に投入できるようになります。また、排出量算定プロセスのボトルネックを把握することで、適切な対策を講じることが可能になります。
さらに、排出量データの信頼性を高めるための具体的なヒントの紹介を通じて、今後の報告実務における精度向上につながる知見が得られるはずです。
この記事を通じて、サステナビリティ開示の実務に自信を持ち、貴社の情報開示品質を一段と高めていただければ幸いです。ぜひ継続的な購読を通じて、変化する基準と実務の最前線をキャッチアップしてください。貴社の未来を支える知識が、ここにあります。