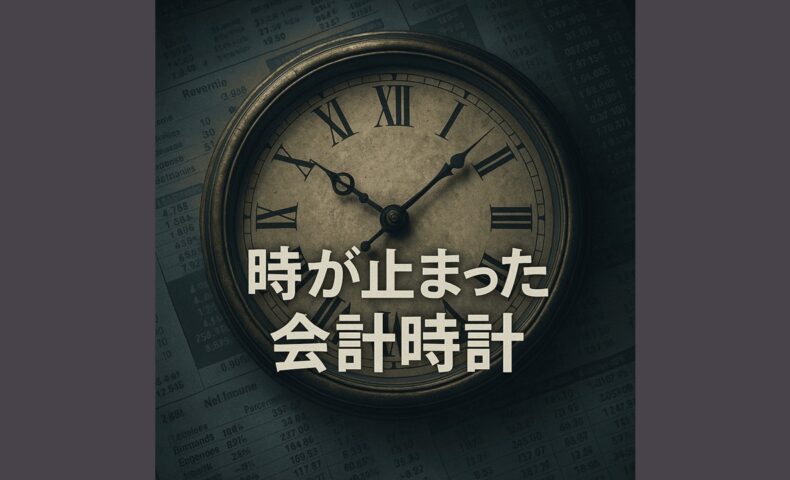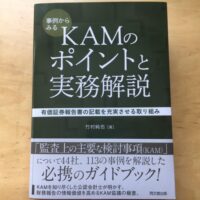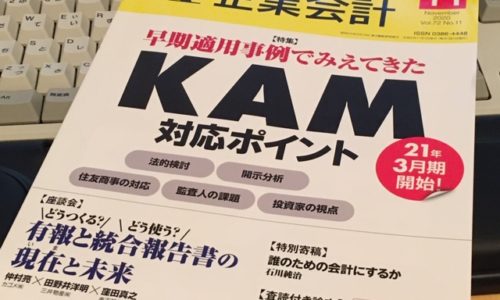2025年10月23日に開催されたセミナー「後発事象の”現行実務”と”基準案”を一挙解説」は、日本の会計基準設定プロセスが抱える構造的矛盾を鮮明に映し出す機会となりました。企業会計基準委員会(ASBJ)が2010年に着手した後発事象に関する包括的な基準開発は、2013年に中断を余儀なくされました。その後、実務指針への「迂回的移管」という流れの中で、2025年にようやく公開草案として陽の目を見ました。
この15年という異例の長期化は、単なる審議の遅延ではありません。国際的整合性と国内実務、理論的整合性と現実的妥協という、相反する要請の間で揺れ動き続けた日本の会計基準設定における「決断の不在」がそこには凝縮されているのです。
■サイバー攻撃が露呈させた制度の盲点
セミナーでは、分析データ「サイバー攻撃が後発事象の評価終了日に与えた影響」を初めて公開しました。これは、理論上の懸念が既に現実のものとなっていることを示す重要な証左です。この分析は、サイバー攻撃を受けた企業の決算実務において、次の三つの時間的区間がどのように変化したかを測定したものです。
- 期末日から会社法監査報告書日までの日数
- 会社法監査報告書日から金融商品取引法監査報告書日までの日数
- 期末日から金融商品取引法監査報告書日までの日数(全体期間)
結果は明瞭でした。サイバー攻撃の発生により、決算完了までの期間が明らかに長期化していたのです。これは、後発事象の評価期間そのものの拡大を意味します。不確実性が高まる状況下での決算遅延は、債権回収不能の判明や希望退職募集の決定など、新たな後発事象を誘発しやすい環境を生み出します。
通常、会社法決算の遅延は、修正後発事象・開示後発事象のいずれにも影響を及ぼすものの、最終的には財務諸表への反映または注記を通じて、適正な開示が担保されます。
問題の核心は、「修正後発事象の例外措置」という特殊な枠組みにあります。この例外措置のもとでは、会社法監査報告書日から金融商品取引法監査報告書日までの期間に発生した修正後発事象は、本来であれば財務諸表の数値に反映すべきであるにもかかわらず、注記による開示で済まされます。
サイバー攻撃によってこの期間が長期化すればするほど、投資家が本来期待する財務情報の確実性は損なわれていきます。不確実性の高い環境においてこそ、投資家は最新の情報が財務諸表の数値に反映されることを求めるはずのところ、現行制度はその期待に応えていません。
■実務家が看破した制度設計の綻び
セミナー終了後、ある受講者から寄せられた「後発事象の公開草案は、このまま進むとは思えない」という言葉は、実務家が持つ制度への深い洞察を端的に表現しています。この直観の背後には、多層的な懸念が横たわっています。
まず、適用指針と会計基準の役割分担に関する根本的な疑問があります。修正後発事象の例外措置という本質的な会計処理の変更を、適用指針レベルで設定することが果たして適切なのか。原則と例外という基本的な枠組みの変更は、重要性の適用を除き、本来は会計基準本体で扱うべき事項です。
次に、手続上の整合性の問題があります。仮にこの例外措置を会計基準本体で設定するのであれば、再度の公開草案が必要となる可能性があります。その場合、単なる形式的な再公表にとどまらず、例外措置そのものの是非を改めて審議せざるを得なくなります。
さらに、会計基準と開示規則の連動性という課題も存在します。仮に会計基準または適用指針で例外措置を設けたとしても、開示規則において「財務諸表の承認の公表日」の注記義務を定めるだけでは、修正後発事象の例外措置まで実効的に条文化できるのか。制度の実効性は、会計基準と開示規則の一体的な整備によって初めて担保されます。
そして最も重大なのは、国際的整合性への懸念です。公開草案どおりに進んだ場合、開示規則に「財務諸表の承認の公表日」の注記義務が設けられても、修正後発事象については例外措置によって財務諸表の数値に反映されません。これはIFRS会計基準や米国会計基準とは明確に異なる取扱いであるため、海外投資家からの疑問や批判を招く可能性があります。日本市場の透明性に対する信頼が問われかねないのです。
セミナーの締めくくりで私は「最終化の審議を注視しながら、新基準への対応に備えよう」と呼びかけました。この言葉には、現状の公開草案がそのまま最終化されるとは限らないという前提が含まれています。
■学界が突きつける理論的脆弱性
公開草案への疑義は、実務界にとどまらず、学界からも提起されています。
明治大学の弥永真生教授は、公開草案へのコメントで、「確認日」を「公表の承認日」と定義することについて、会社法の観点から不適切であると批判しています。会社法における「承認」の概念と、会計基準における「確認日」の定義との間には、法的整合性の問題が存在するというのが弥永教授の指摘です。
また、元ASBJ委員でもあった早稲田大学の秋葉賢一教授は、適用指針に特例的な取扱いを定めることはその本来の役割を超えていると明言しています。適用指針は本来、会計基準の適用方法を明確化するためのものであるため、会計処理の根本原則を変更するような例外措置を設けるべき場所ではないという主張です。
これらの批判は、単なる技術的な指摘にとどまりません。会計基準の体系的整合性、法制度との調和、そして基準設定主体としての説明責任という、より根源的な問題を提起しているのです。
■問われる説明責任と制度の信頼性
ASBJは今後、寄せられた反対意見への対応を検討していきす。通常の手続であれば、公開草案に対するコメントを精査し、また、必要な修正を加えた上で最終基準を公表します。しかし、前述した実務家の直観、学界からの批判、そして定量データが示す実務上の懸念を総合すれば、「このまま進む」ことは考えにくいのです。
仮に公開草案がそのまま最終化されたとしても、それは問題の解決ではなく先送りに過ぎません。フェーズ2での再検討が実現されなければ、修正後発事象の例外措置という本質的な論点は宙に浮いたままです。それは、日本の会計基準に対する国内外の信頼を長期的に損ないかねません。
本件が問いかけているのは、後発事象という個別の会計論点にとどまりません。日本の会計基準設定プロセスにおいて、理論的整合性と実務的配慮をどのようにバランスさせるのか。国際的整合性と国内制度の特性をどう調和させるのか。そして何よりも、基準設定主体としての説明責任をいかに果たすのか。これらの根源的な問いに向き合う必要があるのです。
15年という歳月は決して無駄ではありません。その間に蓄積された議論、浮上した論点、そして明らかになった課題は、今後の基準設定において貴重な教訓となるはずである。重要なのは、この経験を次にどう活かすかです。公開草案の最終化という短期的なゴールにとどまらず、日本の会計基準設定プロセス全体の質的向上という長期的視座から、この問題を捉え直す時が来ています。
実務家、学界、そして投資家を含むすべてのステークホルダーは、この審議プロセスを注視し続けなければなりません。後発事象基準の行方は、日本の会計制度の信頼性そのものを映し出す鏡だからです。