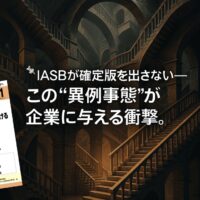「スコープ3は、GHGプロトコルの15カテゴリーを測定しておけば十分なのか?」
IFRS S2号の適用準備が進む中で、企業が最初に直面する論点は、意外にも基礎的な問いから始まります。一見すると算定手法のテクニカルな問題のように見えるこの問いは、実は、移行リスクの“本質”をどこまで捉えに行くのかという、開示戦略そのものの設計に直結しています。
IFRS S2号の付録Aでは、スコープ3温室効果ガス(GHG)排出を「スコープ2に含まれない、企業のバリュー・チェーンで発生する間接排出(上流・下流の排出を含む)」と定義しています。そのうえで、「温室効果ガスプロトコルのコーポレート・バリュー・チェーン(スコープ3)基準(2011年)」における、「スコープ3」カテゴリー、すなわち15カテゴリーを「含む」(include)と記述しています。ここで用いられる「含む」(include)という語は、ISSB基準において一般に「非網羅的な列挙」を意味する用語として用いられるため、スコープ3排出が15カテゴリーに限定されない広がりを持つことを示唆しています。
他方で、IFRS S2号の具体的な要求事項は、スコープ3の測定と開示を明確に15カテゴリー構造に結びつけています。例えば、29項(a)(vi)(1)は、企業が開示するスコープ3排出に含めたカテゴリーを、GHGプロトコルで定義される15カテゴリーに沿って示すことを求めます。さらにB32項は、スコープ3排出の開示にあたり、企業がバリュー・チェーン全体(上流・下流)を考慮するとともに、15カテゴリーすべてを考慮したうえで、どのカテゴリーを測定に含めたかを開示するよう義務づけているのです。
この結果、実務では、「バリュー・チェーン全体」という抽象的な広がりと、「15カテゴリー」という具体的な構造のあいだで、解釈の揺らぎが生じています。ここに問題があるのです。
こうした問題意識に対して、2025年11月にIFRS財団の移行支援グループ(Transition Implementation Group:TIG)に提出されたスタッフ文書(Staff paper 3: Scope 3 GHG emissions applying IFRS S2)は、IFRS S2号の要求と15カテゴリーの関係を丁寧に読み解きながら、スコープ3の“境界線”をどのように解釈すべきかについて整理された見解を提示しています。本稿は、このスタッフ文書の分析を手がかりに、なぜスコープ3の境界線が「コンプライアンス上の線引き」にとどまらず、「企業の移行戦略をどう描くか」というレベルのテーマへとせり上がっているのかを明らかにしていきます。