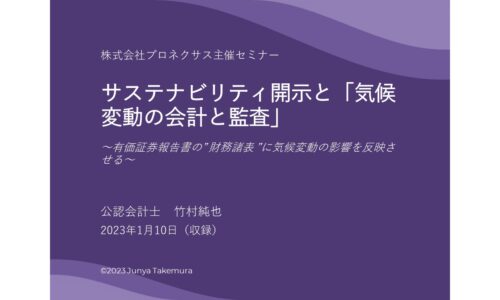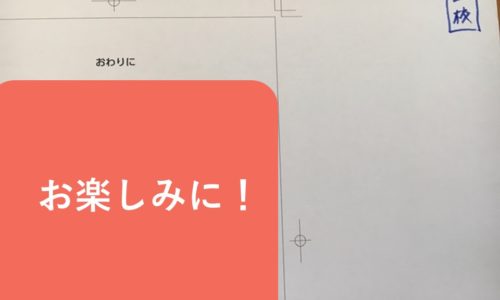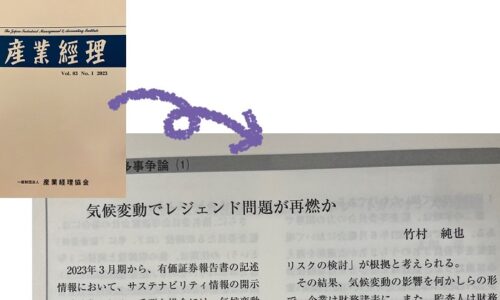2025年12月24日に開催された第61回SSBJ会合。ここで共有された問題意識は、実務家にとってはいささか衝撃的なものだったかもしれません。というのも、これまで暗黙の前提として扱われてきた理解、すなわち、温対法に基づく測定は「ISSB/SSBJ基準における法域の当局が異なる方法を要求している場合」に該当するという理解が、原理的には否定される可能性を完全には排除できない、という指摘がなされたからです。
前回の第60回会合では、議論の焦点はもっぱら実務上の調整にありました。温対法に基づく温室効果ガス排出量の算定・報告制度を所与の前提としたうえで、ロケーション基準相当の数値をどのように算定し、また、どのような注記を付せば利用者の理解に資するか。比較可能性や実務負担を過度に損なわずに制度を運用することが主眼とされ、併せて、こうした国内実務上の取扱いを採る場合には、ISSB基準との同時準拠が困難となる可能性があることを注意喚起する整理も議論されていました。
ところが、第61回会合で前面に出てきたのは、こうした実務調整の可否そのものではありませんでした。議論は、「温対法は、そもそもISSB/SSBJ基準における『法域の当局が異なる方法を用いることを要求している場合』に該当し得るのか」という、測定の前提条件そのものへと立ち戻る形で整理されていったのです。
これは、実務論から理論論への単純な転換というより、これまで暗黙に前提とされてきた理解が、基準の規定構造と整合しているのかを改めて点検する動きと捉えるのが適切でしょう。実務上は、温対法に基づく算定・報告制度は、IFRS S2第29項(a)(ii)およびこれを踏まえたSSBJ気候関連開示基準第49項ただし書きにいう「法域の当局が異なる方法を要求している場合」に該当するものとして理解されてきました。その前提のもとでは、温対法に従って算定されたスコープ2排出量であっても、ISSB基準およびSSBJ基準との整合は図れるという理解が、企業や保証実施者・利用者の間で共有されてきたのです。
第61回会合では、この前提を規定レベルで読み直した場合に、どこまで無理なく支えられるのかが問い直されました。焦点となったのは、「『法域による異なる方法』とは、基準が想定するどの測定要請に対して異なるのか」という、規定の射程そのものです。
SSBJは、ISSB基準の文言を実務の便宜から拡張的に解釈するのではなく、基準が本来想定している測定構造との整合性に立ち戻って検討する必要がある、という問題意識を共有したと理解できます。ここに、第61回会合の議論の重心があるのです。