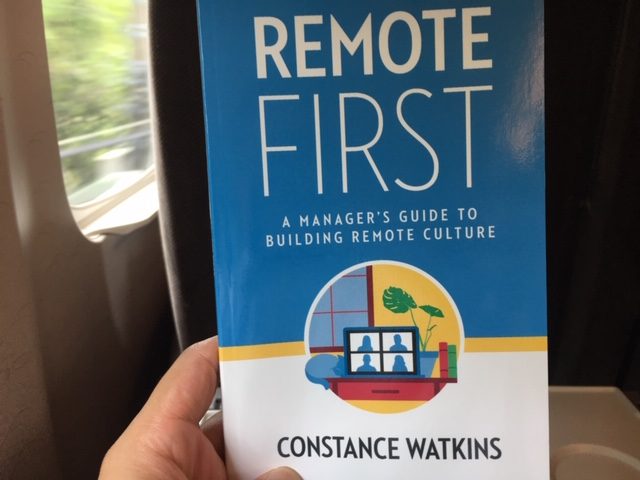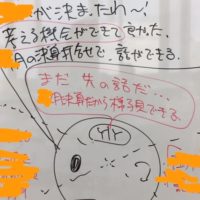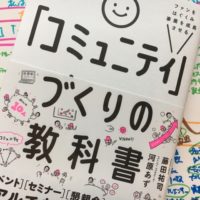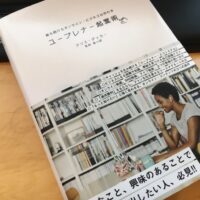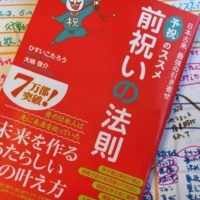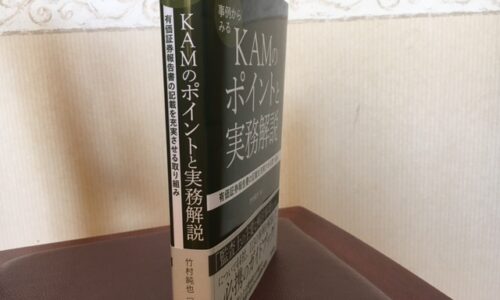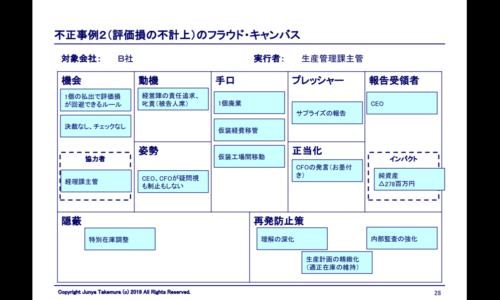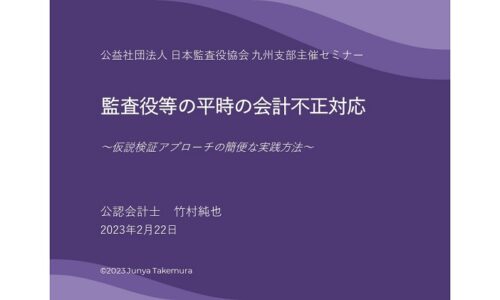理解してもらえないと、人は寂しいもの。
何かの理論でノーベル賞を取るくらいの人は寂しいと聞きます。なぜなら、それを理解できるのは、世界でも僅かの人数のため。
あまりにも先端を走っていると、周りがついていけないことから理解されない。本人が切り開いた光景を誰も見れないために、共感できないのです。
ノーベル賞とまではいかないにしても、日常でも似たような状況に出会うことがあります。ある分野でのミーティングのときに、自分ひとりが詳しいために、他の誰とも話が噛み合わないこと。
単なる世間話のときには、相手にそこまでは求めませんよ、もちろん。それは知っていないのが当たり前だから。また、それを知らないことを責める理由も必要もない。
しかし、ある分野で検討するメンバーに選ばれているにもかかわらず、不勉強なのはダメ。そんな理由で話が理解されないのは、寂しいを通り越して、ただただ呆れるだけ。
以前、教育研修について意見を求められるミーティングに参加したことがあります。呼び出している方も参加している方も、教育研修を担当している方たち。
ところが、ミーティングが進むにつれて、様子がおかしいことに気づきます。参加している方たちは、教育研修を担当されているにもかかわらず、そのことについて何も勉強していない。だから、感情論で話が進む。
その中で、研修アンケートの話題になったときに、ボクが「最も役立ったことについて200時以上の記載を求めている」と話します。すると、他の参加者が、「ウチでも感想文を書かせている」と負けずに被せてくる。
いやいや、感想文と言うんじゃないですから。ボクのほうの取り組みは、研修の内容をどう活かしていくかについて振り返るのが目的。記憶の定着や理解の発展につなげるためのもの。
むやみやたらに感想を書かせてダメな理由は、くそ偉そうな批評で終わってしまうこと。つまり、他人事になっているのです。自分ごとにならないと、学びにはなりません。学びを生み出すためにも、振り返りは必要。
目的がわからずに形だけ真似してみても、十分な効果、期待した効果は得られません。明確な意図を持ったデザインがなければ、再現性のない取り組みで終わってしまいます。そんな取り組みに付き合わされる参加者も、いい迷惑。
今日、呼ばれた教育研修のミーティングでは、議長役の方が、長年、人材開発に携わっていた方。おかげで、ボクの話もすんなり理解してもらえました。
マインド・スキル・ツールの観点からボクが話すと、前のめりになって「そうそう、マインドセットは、〜」と応答してくれましたし。
他にも、アメリカでのオンライン研修の状況にも触れると、その議長役の方は「確かに、あれはすごいよね。〜」とご自身の最近の体験も踏まえて、今後の対応を述べてもいましたし。
こんな具合で、参加者の勉強不足から来る寂しさを感じることなく、ミーティングは終わりました。そんなときに思い出したのが、冒頭のノーベル賞の話でした。
そうそう、オンライン研修と言えば、注文していた洋書が届いていたっけ。コンスタンス・ワトキンス氏による『Remote First: A Manager’s Guide to Building Remote Culture 』。マーケッターの神田昌典さんが激推ししていたので、思わず購入。
オンラインでのミーティングに活用できるんじゃないかと期待しています。今までリアルでのミーティングを重視していましたが、ファシリテーション・スキルを使えば、オンラインでも上手く進行出来そうな感触があるため、その参考にこの本を選んだ次第で。
上手く行くようなら、シェアしていきますね、だって、同じ景色を見たいじゃないですか。あなたはどう思う?