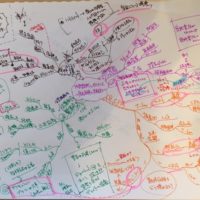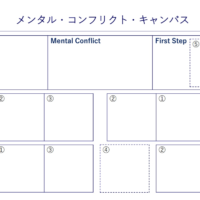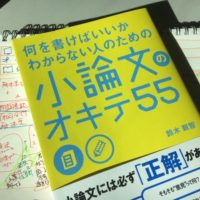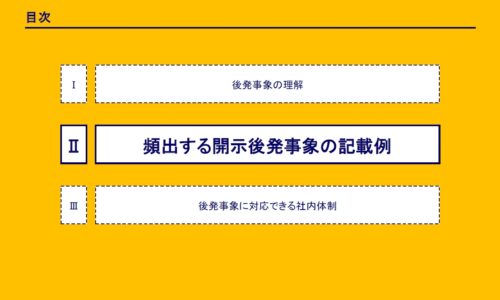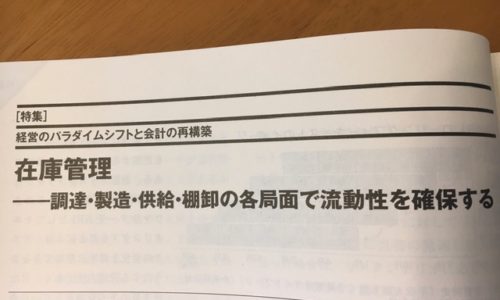あなた、酔ってます?
これ、お酒のことじゃありません。あなた自身のこと。自分自身に酔っているかどうかという質問。組織の中で年次が高まるほど、つまりは偉くなるほどに、自分自身に酔っているかもしれません。
しかし、本人はまったく、そう思っていない。むしろ良いことをしているとすら考えている。だから、始末が悪い。でも、「~すべき」という言葉が並んでいる文章ってありませんか。
これは、「~している自分が好き」と言い換えることもできます。「~すべき」という文章を書いている人は、「こんな良いことを書いている自分が好き」という状況に陥っている可能性があるのです。
ここで紹介したい話があります。ボクの記憶では、確か、『なぜ「教えない授業」が学力を伸ばすのか』(日経BP社)という本。これは、現役の高校教師である山本崇雄サンが、先生が教える授業から、生徒が自分で学んでいく授業の方法を説いたもの。そこで、先生になる人は、基本的に教えることが好きな人が多い、と指摘していたのです。
もちろん、教えることがダメなのではありません。誰かの知識を別の誰かに移転させるためには、教えるという行為が効果的な局面があります。
しかし、問題なのは、主役が先生になっているケース。「教えている自分が好き」という状態になっているのがダメなのです。なぜなら、生徒に目が向いていないから。自分に酔っているだけ。知識を「伝える」ことに関心があるのであって、その知識が「伝わる」ことには関心がないのです。
しかも、やっかいなのは、教えることが好きな人は、悪意がない。そもそも生徒に「伝わる」という発想がないため、いかに「伝える」かにフォーカスしてしまう。意図的に「伝わる」ことを排除していない。ピュアな分、始末が悪いともいえます。
さらに面倒なのが、お偉いさんの書く文章。学校の先生のようなピュアさは持ち合わせていません。「こんなに素晴らしいことを書いたんだから、当然、これに従うよな」という文章を書く。加えて、たった1度、そういうタイプの文章を出しておけば、熟読するだろう、行間まで読み取ってくれるだろう、という文章。ふんぞり返っている様子が目に浮かびます。
そのため、覚えやすいように3つに分類する、といった工夫すらしない。ひたすら列挙するだけで終わってしまう。以前のブログ「ワークショップで伝える順番はこれ」では、三谷幸喜サンの脚本によるフジテレビ系のドラマ『王様のレストラン』での光景を紹介しました。
レストランのオーナーが朝礼で、最初は「3つのW」や「5つのP」として教訓を話していました。これが、「37のS」になってしまう、というオチ。そんなに多くては、とても覚えられません。
先日も、とある資料で「17の提言」と記載されていたのを見て、苦笑しましたよ。実際、中身をみると、レベル感の異なるものが列挙されているだけ。その順番にも意味を読み取れない。ビジネスの場でのプレゼンだと、「17の・・・」と話した途端にそっぽを向かれてしまいます。
この資料を作成した組織には、「伝わる」ことに関心がある人が誰一人いなかったのでしょうね。あるいは、声を挙げた人がいても、そのことに耳を傾ける人がいなかったか。
もう少し、読み手に寄り添った文章にすると、書き手が呼びかける行動をとってもらいやすくなる。せっかく時間をかけて作った文章なのだから、自己満足で終わってはもったいない。
自分に酔った文章じゃ、誰も付き合ってくれません。そろそろ、酔いから覚めませんか。