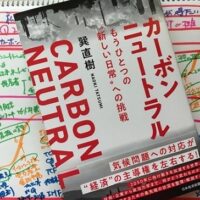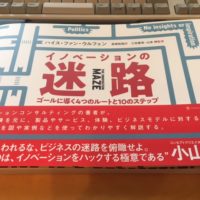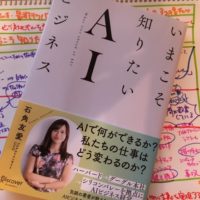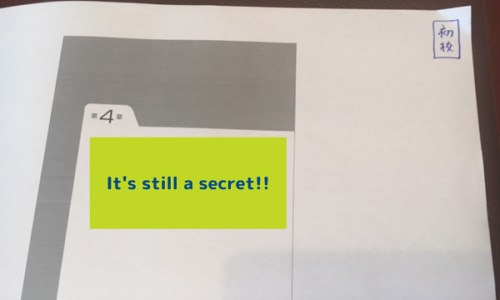テレビで、見知った方のお顔を見ると、ちょっとテンションが上がりますよね。「おお、あの人がテレビに映っている!」って。
つい最近、そんな経験をしました。テレビのニュース番組に、なんと、JICPAの会長を務めていらした、増田宏一サンのお顔が映っているじゃありませんか。そのお隣りには、八田進二サンもいらっしゃいます。
これ、増田元会長が座長を務めている学校法人ガバナンス改革会議に関するニュースでした。2021年12月3日付で、「学校法人ガバナンスの抜本的改革と強化の具体策」という報告書が公表されています。その報告書を文部科学大臣に提出した様子が、映像となって報道されたのです。
実は、この会議について、発足された当初からウオッチしていました。ちょうど、コーポレートガバナンス・コード対応の支援業務に携わっていたり、私立学校の監査に縁があったりとしていたため。
議事要旨のチェック
で、この報告書に目を通す前に、議事要旨をチェック。こういった審議過程から、何が問題視されていたのか、どのような議論があっての結論なのかがつかめるため、報告書の内容をより理解できるからです。
第1回から、随分とバチバチした様子が記されています。その先行を心配しながらも、第3回の議事要旨にたどり着きます。これが興味深いのなんのって、気付きのオンパレード。
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/115/gijiroku/mext_00003.html
この第3回には、オブザーバーとして、株式会社経営共創基盤共同経営者(パートナー) IGPIグループ会長である冨山和彦サンをお招きしていたから。書籍も多く、著名なお方。最近は、こんな本も出されています。
オススメの第3回の開催模様
講演の内容は、「全ての組織に共通のガバナンスの要諦」です。組織の形態を問わずに求められるガバナンスについて説明をしたうえで、大学組織のガバナンスの特徴が挙げられます。これに関して質疑応答も含めると、日本の私立大学が実は国立大学であることが指摘されます。
引き合いに出されたのは、アメリカの州立のカリフォルニア大学。カリフォルニア州とは、5年に1回ごとの契約だそうです。5年契約で州税を受ける一方、その反対給付として何を提供するかを毎回契約し直す、とのこと。州からお金をもらうと対応が大変なため、州税を受け取らないプライベートの私立大学になるかどうかの議論があるようです。
その意味で言えば、日本の私立大学は私学助成を国から受け取っているため、アメリカでいうところの国立大学なんだそうで。なるほどと思う反面、驚きでもありました。確かに、大学運営の資金のほぼすべてを助成金で賄っていたら、それは国の運営といっても過言ではありません。
以前、大学の先生から、研究費をもらえる感覚になるからダメになる、つまりは自立できない旨のお話しを伺ったことがあります。これが、大学でも起きていることが理解できました。
米国大学のビジネスモデル
また、米国の有力大学のビジネスモデルにも驚き。それは、アラムナイ(卒業生)の活用です。
卒業生が経済的に成功すると、寄付があったり、産学連携を通じた研究資金をもたらしたり、ベンチャー投資による利潤だったりと、巨額の資金が得られると、それを大学運営に使えます。それが循環するメカニズムのビジネスモデルになっているため、人材の取り合いが凄い。
なぜなら、将来有望な学生がどの大学のアラムナイとなるかどうかで、その大学の将来の財政が決まってしまうから。引き抜きは、研究者だけではなく、学生でも行われているようです。すごくないですか、この話。
ビジネスモデル・キャンバスに照らすと、有望な学生は、大学生の頃は「顧客」であり、また、卒業して大成すると「キーパートナー」となるのです。顧客としての授業料収入に加えて、その後、キーパートナーとして各種の資金をもたらしてくれる循環モデルとなっています。
この循環モデルは、経営としてはもちろんのこと、教学としても有益ですよね。こういう発想で大学経営が行われるためには、外部の人材の活用が必須。こうしたモデルを築き上げている学校法人が極めて少ないですからね。
就職予備校で良いかは個人的に疑問
ただ、気になったのは、大学をグローバル型とローカル型に分けたうえで、教育の内容も分ける、との話。ローカル型の大学は、学生を集めるためには、職業型教育にならないとダメだといいます。
それでは、大学が企業のために存在することになります。それは、社会に出てからでも身に付けられます。そうではなく、教養を身につけることが、社会で何を行うときにベースとなるかと。
もしかすると、各論を詰めていけば、同じ状況を見ているのかもしれません。ただ、総論で進むと、人によって誤解が生まれそうな主張だったのが気になりました。
DX、DX、DX!!!
もっといえば、大学という枠にとらわれずに、DXを活用した方策もあるかと。例えば、大学という日本でただ一つのウェブサイトに、大学生ならアクセスできる、という仕組み。大学が設置された場所にとらわれることなく、良質なコンテンツを受講できることのほうがメリットは大きいハズ。授業内容の水準によって自ずと受講生は限られます。
もちろん、対面でしかできない授業は、物理的な大学に行く必要は残ります。しかし、2022年にもなって、物理的な制約に100%とらわれる必要はありません。そのほうが、教えることが不得手な人が授業するよりも、生徒も先生もハッピーです。まあ、この改革会議の性質上、そこまでの提案までは求められていないのでしょう、残念です。
そうそう、もう一つ驚いたのが、この学校法人ガバナンス改革会議の開催模様が、YouTubeでも視聴できること。確かに、文部科学省のチャンネルに、動画がアップされていました。もう実践しているじゃないですか。案外、灯台下暗し、かも。
話を戻して、議事要旨を読むより、動画を視聴したい、という方は、こちらからどうぞ。所要時間は、1時間10分57秒です。