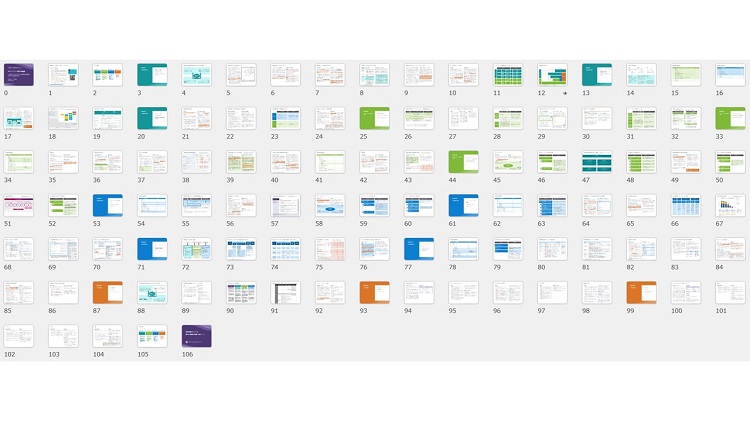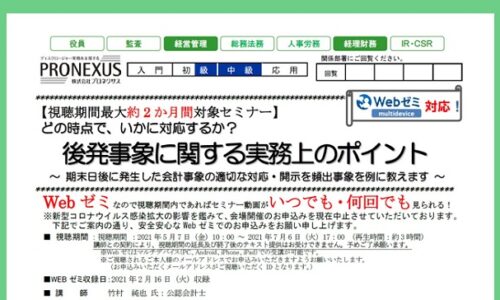サステナビリティ開示の動向を理解するために、最も適した方法とは何か。
これは、セミナーの控室で、主催者側と話していた内容のひとつです。昨日の2023年12月1日、一般財団法人産業経理協会さんの主催セミナー「サステナビリティ開示の最前線」で講師を務めてきました。
結論からいえば、サステナビリティ開示についてはセミナーが最適なのではないか、ということ。こうした考え方のきっかけには、メディアアーティストであり、筑波大学准教授でもある落合陽一サンによる次の動画がありました。
- 【落合陽一のシンギュラリティ論】シンギュラリティは2025年に来る/ディフュージョンモデルの衝撃/知的ホワイトカラーが没落する/最新版デジタルネイチャー/音楽と論文が数秒でできる
この中で、毎分、技術が進化すると、人間の理解が追いつかないと説明します。例えば、10万年くらい変化しない昆虫を対象とする場合、元来の自然の世界では、時間をかけて観察・研究した結果を論文にできました。しかし、例えば、観察の都度、進化していくAI技術を対象とする場合、デジタルネイチャー(計算機)の世界では、論文を書いてもその対象が変化している、といいます。
また、「もし10秒で査読に5日かかる論文を生成できるとするならば、我々は本当に論文を読むだろうか」とも投げかけます。その結果、「情報の消費活動の主体がコミュニケーションにあるならば我々は静的パッケージから動的イントラクションに移行するだろう」と主張します。
ここから理解できるのは、変化のスピードが早いものを対象とする場合には、静的パッケージでは限界があること、また、動的インタラクションとして直接、質問できるような場が適していることが理解できます。
すると、サステナビリティ情報の開示にも、これと同じことが当てはまるのではないでしょうか。次から次へと新しい情報が登場するからです。実際、2ヶ月前にも産業経理協会さんで同じテーマのセミナー講師を務めたものの、今回のセミナー資料で扱う内容のいくつかは、最新情報を提供するためのアップデートが必要でした。
また、紙媒体では、サステナビリティ関連の書籍は、まだまだ少ないのが現状です。原稿を提出して出版に至るまでに3ヶ月近くの時間を要すると、発売した瞬間に内容の一部が陳腐化してしまいかねないからです。一度、確定した後、しばらくは変更のない基準や制度を扱わない限り、書籍で学ぶことには限界があります。また、サステナビリティ開示は活動を伴う必要があるため、後でゆっくりと学んでいては、対応のための時間を十分に確保できない状況を招きます。
その意味では、定期的に発行される専門雑誌のほうが、キャッチアップしやすいでしょう。毎月、隔月、毎週という頻度で情報が得られるからです。編集者の目を通るため、品質にも信頼性が持てます。ただし、企画、執筆依頼、執筆作業、校正、印刷、流通という作業過程を経るため、そう長くはないものの、一定の時間を要するのも事実です。
よって、こうした静的パッケージよりも、動的インタラクションであるセミナーのほうが、より最新の情報を得る目的には適っています。特に信頼のある講師や主催者による開催であれば、品質に大きな問題もないでしょう。
迅速性でいえば、今回のセミナーの場合、3日前の2023年11月28日に開催されたSSBJの審議状況まで補足説明することができました。また、インタラクションでいえば、当日、会場でリアル参加された方々とは、セミナーの時間内や終了後の質疑に応答しています。
なお、今回のセミナーは、2023年12月28日まではオンデマンド配信を視聴できます。浅すぎず深すぎずの内容で、また、具体的にイメージできるよう海外事例も盛り込んだ3時間セミナーです。セミナー資料は後日の使用にも耐えられるよう、このブログのトップ画像のとおり、スライド総数106枚と内容をしっかりと書き込んでいます。
情報が新鮮なうちに、受講されてはいかがでしょうか。