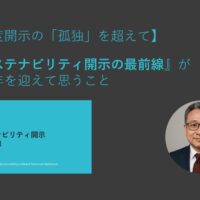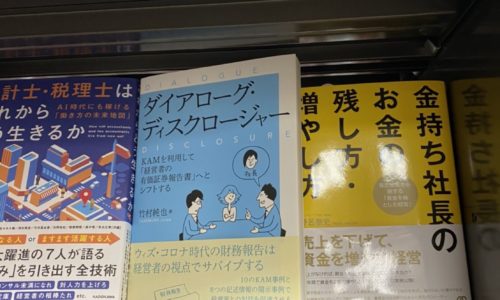「この資料、開示要件が網羅されていて、本当に助かります」
ある受講者のひとことが、すべてを物語っていましたね。これは、2025年5月30日開催のセミナー「【新基準対応】サステナビリティ開示の全貌と実務ポイント」での出来事です。
おそらくその声は、心からの感謝とともに、現場が抱える静かな悲鳴でもあったのでしょう。知っているはずなのに、動けない。そんな組織の苦悩を、私は確かに感じ取りました。
日本のサステナビリティ基準(SSBJ基準)が2025年3月に最終化されたことで、いよいよ企業は「対応フェーズ」へと足を踏み入れたわけです。しかし、ISSB基準と整合するSSBJ基準の定めは、実施に関するものから開示に関するものまで幅広く、かつ、極めて精緻なものです。
こうした膨大な要件への対応において、現場では「何から着手すべきかわからない」「どこまで進捗しているか把握できない」「どの開示要件が漏れているか不安」といった混乱が生じているのも無理はありませんよね。
この実務上の課題を解決する秘密兵器として開発したのが、「開示の構造コンパス」です。
■SSBJ基準「要件ジャングル」から脱出する唯一の方法
多くの企業が陥っている「要件ジャングル」から抜け出すためには、根本的な発想の転換が必要です。
この構造コンパスは、単なる要件の一覧化ではありませんよ。それは、開示対応を具体的に動かすための実務的な設計図に他ならないのです。シンプルな構成でありながらも、開示要件を漏れなく網羅している点に特徴があります。
まず、SSBJの一般基準、気候基準のそれぞれで、4つのコア・コンテンツ(ガバナンス、戦略、リスク管理、指標及び目標)ごとの開示要件を意味のある内容で分類します。
たとえば、「戦略」の開示には大きな流れがあります。まずリスクと機会を特定し、次にその影響を評価し、最後に対応する、という一連のストーリーですよね。ただし、影響については開示要件が多岐にわたるため、構造コンパスでは、①リスク・機会、②影響(ビジネスモデル&バリューチェーン)、③影響(財務)、④影響(戦略・意思決定)、⑤レジリエンスという5つのカテゴリーに分類しています。
次に、コア・コンテンツごとの分類を3つの視点で区分します。戦略を例にとれば、先ほどの5つの分類に共通する実務的な視点を設定するのです。この視点には開示実務のプロセスを意識した工夫が込められているのですよ。
最後に、これらの分類と視点を掛け合わせたマトリックス表に、開示要件を基準の項番やより詳細な単位で配置します。重要なのは、ひとつの開示要件は必ずマトリックス表のひとつのセルにのみ配置するということです。複数のセルにまたがって配置することはありません。つまり、開示要件の漏れの完全防止、重複作業の排除、進捗状況の可視化を実現しているのです。
こうして開示要件を構造化することで、企業は次のような重要な問いに即座に答えられるようになりますよ。
- 現在、どの領域の開示対応が順調に進んでいるか?
- どの要件が未着手で、どこにギャップがあるか?
- 継続的な改善につながっているか?
このように、構造コンパスは単に理解を助けるためのツールではなく、実装までも強力に促進する実践的な装置なのです。
■従来のESG開示が通用しない「根本的な違い」とは?
構造コンパスには、一般基準と気候基準を対象とした「開示の構造コンパス」に加えて、適用基準を対象とした「開示作法の構造コンパス」も用意されています。これが実に巧妙な設計なのです。
ISSBやSSBJが求めるサステナビリティ関連財務開示は、従来のサステナビリティレポートとは根本的に異なります。なぜなら、「関連する財務諸表」を補足する情報開示であるため、会計の開示作法が色濃く反映されているからです。
しかし、この適用基準が要求する事項も膨大です。理解するだけでも一苦労なのに、実務対応で作法迷子になってしまっては元も子もありませんよね。
そこで、適用基準の多数の要件について、4つの分類と3つの視点のマトリックス構造に再構築しました。これが「開示作法の構造コンパス」です。これにより、理解を促進するだけでなく、プロセス管理も可能となります。CFOとの議論もスムーズになるでしょう。
■「コンプライアンス消費」で終わる企業と「未来創造」企業の分岐点
「開示の構造コンパス」があることで、担当者は迷いやく作業を進められます。経営層と建設的な議論が可能になります。プロジェクトが確実に前進します。そして何より、「やっているつもり」から「やれている実感」に変化します。
SSBJ基準は、確かに開示基準ですが、同時に組織の思想や価値観にも深く関わります。単なる「コンプライアンス消費」として最低限の対応で終わらせてしまうのか。それとも、未来への問いかけとして、自社の価値創造プロセスと一体化させていくのか。どちらを選ぶかが、企業の将来の競争力を大きく左右することになるでしょう。
構造がなければ、理想を現実に変えることはできません。けれども、適切な構造があれば、誰でも、どんな組織でも始めることができるのです。それが、私がこのツールを通じて見出した確信でした。目指すべきは、「実装の扉」を確実に開くことです。
もしあなたが今、SSBJ基準の膨大な要件を前に立ち止まっているなら。もしあなたが「理解はできたが動けない」という分析麻痺の状況にあるなら。
このツールは、まさにそのような状況にある方々のために、全力で作り上げたものなのです。