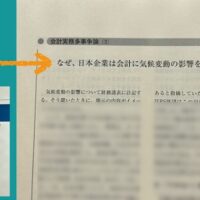2025年7月17日、金融審議会の「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」が公表した『中間論点整理』は、日本企業のサステナビリティ開示制度に重要な転換点をもたらします。これは、同年3月から継続されてきた審議において、企業の予見可能性確保を目的として現時点での議論状況が整理されたものです。
https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20250717.html
最も注目すべきは適用企業の範囲ですよ。SSBJ基準の適用が株式時価総額を基準とした段階的導入スケジュールとして次のとおり明示されました。
- 株式時価総額3兆円以上の企業:2027年3月期
- 株式時価総額3兆円未満1兆円以上の企業:2028年3月期
- 株式時価総額1兆円未満5,000億円以上の企業:2029年3月期
ただし、1兆円未満5,000億円以上の企業については、2029年3月期を基本としながらも国内外の動向を踏まえた継続検討が必要とされ、また、年内結論が適当との見解が示されました。さらに重要なのは、株式時価総額5,000億円未満のプライム企業については、基準適用と保証導入を今後の状況を見ながら検討し、かつ、数年後に結論を出すことが適当とされた点です。これが一部報道において「全プライム企業への義務化見送り」として報じられる根拠となったのですね。
こうした発表を受け、時価総額5,000億円未満のプライム企業は開示負担の軽減を歓迎しているかもしれません。しかし、この判断は企業価値評価において重大なリスクを内包していることを看過してはなりません。なぜなら、開示の有無が投資家の企業理解を根本的に左右する構造が既に生まれているからです。