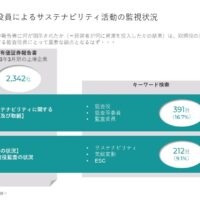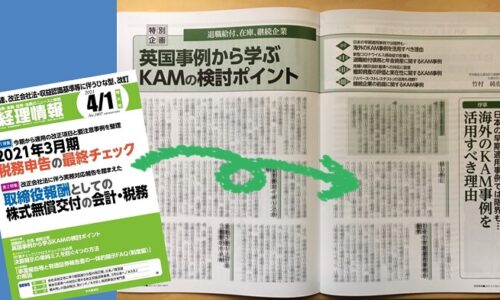2023年9月18日、ついに、TNFD提言の最終版がリリースされました。TNFDとは、自然関連財務情報開示タスクフォース(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures)のことです。自然や生物多様性に焦点を当てた、サステナビリティ開示のフレームワークが完成したのです。
そのリリース文の「Final TNFD Recommendations on nature related issues published and corporates and financial institutions begin adopting」(仮訳「自然関連問題に関するTNFD提言の最終版が発表。企業や金融機関が採用開始」)に、気になる点がありました。それは、ISSBのスー・ロイド副委員長によるコメントです。その内容を抜粋・仮訳すると、次のとおりです(P.4)。
我々は、ともにTCFD提言の構造を組み込んでいる、最終化されたTNFD提言とISSB基準とが高いレベルで整合していることを喜ばしく思います。我々は、投資家に一貫性のある包括的なサステナビリティ関連開示を提供するため、開示状況の簡素化に努めながら、TNFDの作業(今後の優先事項に関する最近の協議の結果次第)を検討していきます。
ここで気になった点は、「開示状況の簡素化に努めながら」の箇所です。両者の差異は、何もTNFD提言がISSB基準よりも開示範囲が広くなるとは限りません。その反対に、ISSB基準の開示要件を満たしていない可能性もあります。
これについて、ドラマ『古畑任三郎』を紹介しておくと、理解が進むでしょう。1999年4月13日に放送された「若旦那の犯罪」の回で、ある刑事が、真犯人である若旦那に対して、事件当時の聞き込みを行います。このときに若旦那が「いつ死んだのか」と尋ねなかったことから、主人公である刑事の古畑任三郎が若旦那のことを怪しみます。なぜなら、真犯人はその時刻を知っているため、尋ねる必要がないからです。
この話を踏まえると、スー・ロイド氏が、なぜ「開示状況の簡素化に努めながら」と話したかの理由が見えてきます。それは、ISSB基準よりもTNFD提言のほうが開示要求の多いことを知っているからに違いありません。ドラマでは、知っているからこそ言葉にしませんでした。一方、スー・ロイド氏のコメントでは、知っているからこそ言葉にしたものと推察できます。どちらも、既知の情報によって行動に影響を与えた点が共通しています。
では、どこが過剰なのか、それについてショートレビューした結果を共有します。具体的な違いはどこなのか、また、それは将来、ISSB基準に取り込まれることがある場合に削除されるものなのかを考察しました。TNFD提言に沿った開示を進めていく際に参考にしたいときには、サブスクリプション・サービスにログインして、読み進めてください。