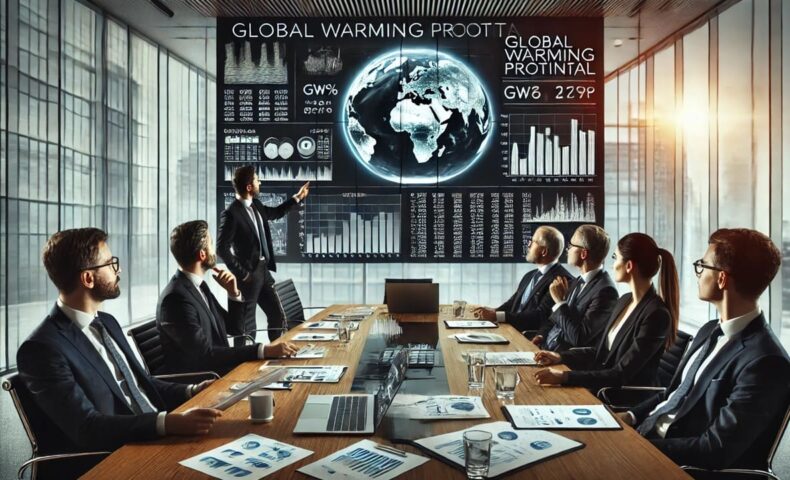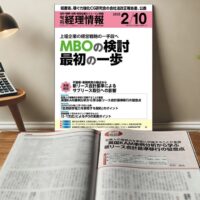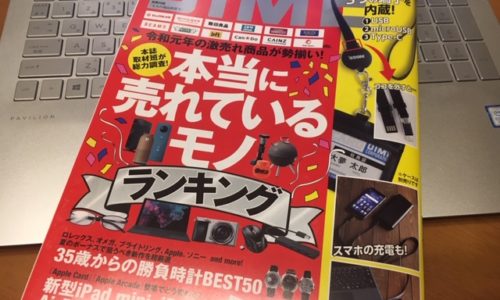2025年1月23日開催の第47回SSBJ会議では、2024年11月に公表された公開草案「指標の報告のための算定期間に関する再提案」に対するコメント対応が主要な議題となりました。この中で筆者が提出したコメントは、温室効果ガス(GHG)排出量のCO2相当量への換算過程における地球温暖化係数(GWP)値の取扱いについてです。
GHG排出量は、次の2つのステップで算定されます。
- 活動量からGHG排出量への変換
- GHG排出量をCO2相当量への換算
このうち後者の換算過程において用いられるGWP値が古い場合、そのまま適用してよいのか、それとも最新のGWP値に置き換えるべきなのかが議論の焦点となっています。2024年9月にISSBの移行支援グループは、各国の規制当局が異なるGWP値を要求する場合には、IPCCが提供する最新のGWP値に基づくべきであるとの見解を明確に示したためです。
一方で、第42回SSBJ会議では、温対法(地球温暖化対策の推進に関する法律)に基づきGHG排出量の測定をGHGプロトコル(2004年)とは異なる方法で行う場合、企業の負担軽減を目的とする容認法を適用したときには、最新のGWP値による再計算を不要とする方針が確認されています。
2024年11月の公開草案の提案が採用された場合、最新のGWP値を用いない方針が引き続き適切かどうかを再検討する必要があると考えたため、筆者はコメントを提出しました。
■SSBJ会議での議論と委員の見解
筆者のコメントは個別の審議資料にはならなかったものの、コメント対応表(案)の全体的な検討に含められました。その中で、あるSSBJ委員が筆者のコメントとSSBJ事務局の見解に注目しました。両者について「GWP値と排出係数のどちらを論点としているのかを明確にすべき」と指摘したのです。この指摘を受け、SSBJ委員長は次のように回答しました。
まず、法域の制度が最新のGWP値とは異なるGWP値を使用することを要求する場合の現行の取扱いです。具体的には、GWP値が組み込まれた換算係数をそのまま適用する、もしくは、その換算係数を分解して最新のGWP値に置き換える対応を取るかのいずれかです。
次に、ISSBの基準修正に関する動向です。現在、IFRS S2基準の修正が検討されていることを紹介しました。そこでは、法域が定めた換算係数が存在する場合、最新のGWP値でなくとも使用可能とする方向で議論が進んでいると説明します。英国やカナダから基準の見直しを求める声があったため、修正の可能性は高いと見込んでいます。
これらを踏まえ、ISSBがこの修正を進める場合には、温対法に基づく換算係数を用いることが認められるため、SSBJの見解、すなわち最新のGWP値による再計算は不要とする見解は妥当であるとの説明がありました。
■IFRS S2基準修正の不確実性とSSBJ基準の安定性
第42回SSBJ会議では、審議の過程で、温対法の排出量計算がCO2換算係数を使用することに基づき、最新のGWP値の適用をめぐる2つの見解が整理されました。
そのひとつは、温対法に基づく測定は政令に基づくGWP値を含むとする見解です。企業は「省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム」に活動量を入力すれば、政令で定められた排出係数とGWP値が自動適用されます。そのため、企業側で再計算する必要はないと解釈します。ISSBの移行支援グループの見解とは異なるものの、日本の実務に沿った対応となります。
もうひとつは、既に当局に提出した直近のデータを用いるべきとする見解です。2024年3月の公開草案では、容認法の目的は企業の負担軽減にありました。したがって、最新のGWP値への再計算は不要とする立場です。
しかし、こうした整理は、2024年11月の公開草案に至る検討を行う直前の議論で行われました。2024年11月の公開草案では、報告期間におけるGHG排出データの算定方法の調整が提案されているため、規制当局に提出したCO2相当量を加工する必要が生じます。そのため、現行のIFRS S2基準と整合を図るのであれば、最新のGWP値を用いることが求められる場面が想定されるのです。
■戦略的対応と今後の展望
第47回会議におけるSSBJ委員長の説明は、IFRS S2の基準修正を前提としたものです。つまり、修正が実現すれば温対法の換算係数を用いることに問題はないとする見解です。しかし、これは逆に言えば、現行のISSB基準に基づく場合、温対法であっても最新のGWP値を使用しないことが認められないことを意味しています。
筆者は、日本企業の負担軽減を否定する立場ではありません。しかし、現時点ではIFRS S2の修正案すら公表されていないため、将来的な修正を前提としてSSBJ基準を最終化することに懸念を抱いています。基準の不確実性が高い中で、実務の安定性を損なう決定を下すべきではないと考えます。
したがって、現時点ではISSBの移行支援グループの見解に沿い、容認法を適用する場合であっても最新のGWP値を使用する方向で解釈すべきです。ただし、これはSSBJ基準そのものに記載するのではなく、解説記事などを通じた説明でも十分だと考えられます。その際、IFRS S2の修正が進んだ場合の対応方針も併記することで、企業や利用者にSSBJ基準の改訂に向けた準備を促すことが望まれます。
このような段階的な対応を取らなければ、仮にIFRS S2が修正されなかった場合、SSBJ基準が実務と整合しないリスクが生じるため、混乱を招く可能性があります。基準の安定性と実務の確実性を両立させるためには、慎重な対応が求められます。
しかしながら、SSBJ基準は2025年3月末までに最終化される予定であるため、ここで提案した対応策が採用されることはないでしょう。企業や利用者にとって、SSBJ基準の不確実性が解消されるかどうかは、IFRS S2の修正動向に依存します。その公開草案が公表されるかどうか、また、公表された場合に期待される内容が提案されるかどうかについて、今後の動向を中止する必要があります。