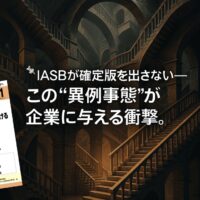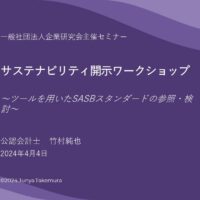「親会社と連結子会社の間で行われる取引に伴う温室効果ガス排出は、グループ全体としてどう扱われるべきなのか」
IFRSサステナビリティ開示基準の適用開始を前に、この問いは実務の現場に最も深い混乱をもたらしてきた論点の一つです。その根底には、GHGプロトコルが企業単位でスコープ分類を定義しているのに対し、IFRS S1号は財務諸表の報告企業をサステナビリティ関連財務開示の単位として採用するという、二つの異なる枠組みの併存があります。
日常的な企業活動を例に取れば、連結子会社が製造した製品を親会社が仕入れるという取引において、連結子会社の下流スコープ3、親会社の上流スコープ3をどこまで認識すべきか、そしてそれをグループ全体としてどう統合するのか。多くの企業がこの判断に迷ってきたのは、財務報告とサステナビリティ開示という二つの世界をどのように接続すればよいのかが明確でなかったためです。
こうした実務上の不確実性に対し、2025年11月、IFRS 財団のTIG(移行支援グループ)のスタッフ文書 “GHG emissions from transactions between entities within a reporting entity”は、財務報告との整合性を軸に、内部取引に紐づく排出の扱いを明確化しました。本稿は、この文書を実務家の視点から解説しながら、その背景にある論理構造と、現場で生じやすい誤解の所在を明らかにします。