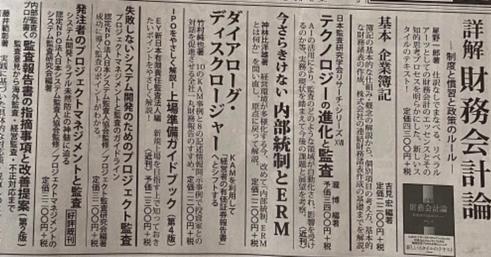2023年6月、ISSBは、2つのIFRSサステナビリティ開示基準を公表しました。そのうち、S1基準と呼ばれているものが「サステナビリティ関連財務情報開示に関する全般的要求事項」です。これは、「一般目的財務報告の利用者のニーズを満たすことに焦点を当てた」サステナビリティ開示を求めています。
一方、日本では今後、SSBJが、ISSBのS1基準に基づき日本版S1基準を設定していく予定です。これが公表された後に、有価証券報告書におけるサステナビリティ開示に適用される見込みです。すると、その開示は、「一般目的財務報告の利用者のニーズを満たすことに焦点を当てた」ものが求められると考えられます。
これに対して、2023年3月期からの有価証券報告書で強制適用となったサステナビリティ開示では、「当連結会計年度末における連結会社のサステナビリティに関する考え方及び取組の状況」の記載が要求されています。そのため、必ずしも「一般目的財務報告の利用者のニーズを満たすことに焦点を当てた」開示にはなっていない事例も存在するものと考えられます。
この場合に日本版S1基準が適用されると、それまでの開示と整合しない状況に陥ります。開示してきたサステナビリティ情報を除外する、あるいは、他のサステナビリティ情報を追加するといった対応に追われるのです。そのときまでに何も対応を図らなければ、将来的に開示が不要となる情報を開示するために社内のリソースを費やすことになります。このような効果も効率も得られない作業は、回避したいところでしょう。
もっとも、日本版のS1基準が適用される際に、そうした不整合を不問とするような制度上の手当がなされるかもしれません。しかし、その保証はないことから、自社として先手を打つことが合理的な判断といえます。今のうちから、ISSBのS1基準が示すプロセスに従って「企業の見通しに影響を及ぼすと合理的に予想されるサステナビリティ関連のリスク及び機会」を識別しておきたいところです。
そこで今回の記事では、ISSBのS1基準に従うと、どのようにサステナビリティ関連のリスク及び機会を識別していくかについて、3つのプロセスを解説します。このうちSASBスタンダードの参照・検討プロセスについては7ステップで整理しているため、今すぐ実務に活用できます。