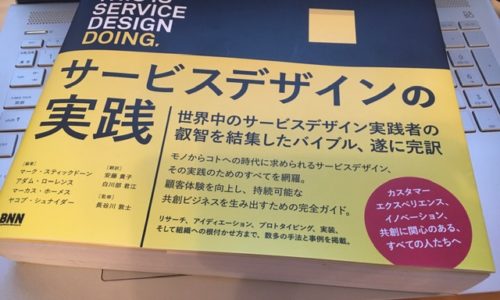サステナビリティ開示に関するガイダンスの情報源について、ここまで議論になるとは驚きです。
2023年12月11日に開催された第27回SSBJの審議は、なんと、1時間18分50秒もの時間がかかりました。ISSB基準が確定された後の第18回から第27回までの審議事項のうち1時間超えとなったものは7件です。その中でも、3番目の長さです。
| 順位 | 長さ | 回次 | 審議事項 |
| 1 | 1時間55分49秒 | 第25回 | スコープ3温室効果ガス排出の絶対総量の開示における重要性の判断の適用 |
| 2 | 1時間23分5秒 | 第23回 | 絶対総量の開示における重要性の判断の適用 |
| 3 | 1時間18分50秒 | 第27回 | ガイダンスの情報源 |
| 4 | 1時間10分37秒 | 第27回 | スコープ2温室効果ガス排出の測定におけるロケーション基準とマーケット基準 |
| 5 | 1時間10分1秒 | 第24回 | 温室効果ガス排出の測定方法の開示 |
| 6 | 1時間4分56秒 | 第27回 | 産業横断的指標等(気候関連のリスク及び機会並びに投下資本) |
| 7 | 1時間3分58秒 | 第23回 | 気候関連の指標及び目標 |
ガイダンスの情報源に関する審議動画を視聴していたときに、ふと、「財務諸表は記録と慣習と判断の総合的表現」という言葉が思い浮かびました。これは、会計学を学ぶときに最初の方に登場する言葉です。これに続く学習では、慣習として発達したものの中から、一般に公正妥当と認められたところを帰納要約されたものが会計原則とされることです。もっとも、最近では、概念フレームワークに基づいた演繹的なアプローチによって会計基準が作成されている側面が強いかもしれません。それは、さておき。
この状況は、サステナビリティ開示基準においても共通点が見られます。アルファベット・スープと揶揄されるほどにフレームワークや基準が乱立していた状況は、まさに複数の「慣習」が成立していたといえるでしょう。また、ISSB基準が、その中から「一般に公正妥当と認められたところ」を採用した点も会計原則と共通しています。
しかし、「帰納要約」という点には疑問が残ります。これは、ISSB基準の構造的な問題とも言えます。そこで、今回の特別記事では、第27回SSBJにおけるガイダンスの情報源の審議を踏まえて、企業がどのような状況に直面する可能性があるかについて解説していきます。